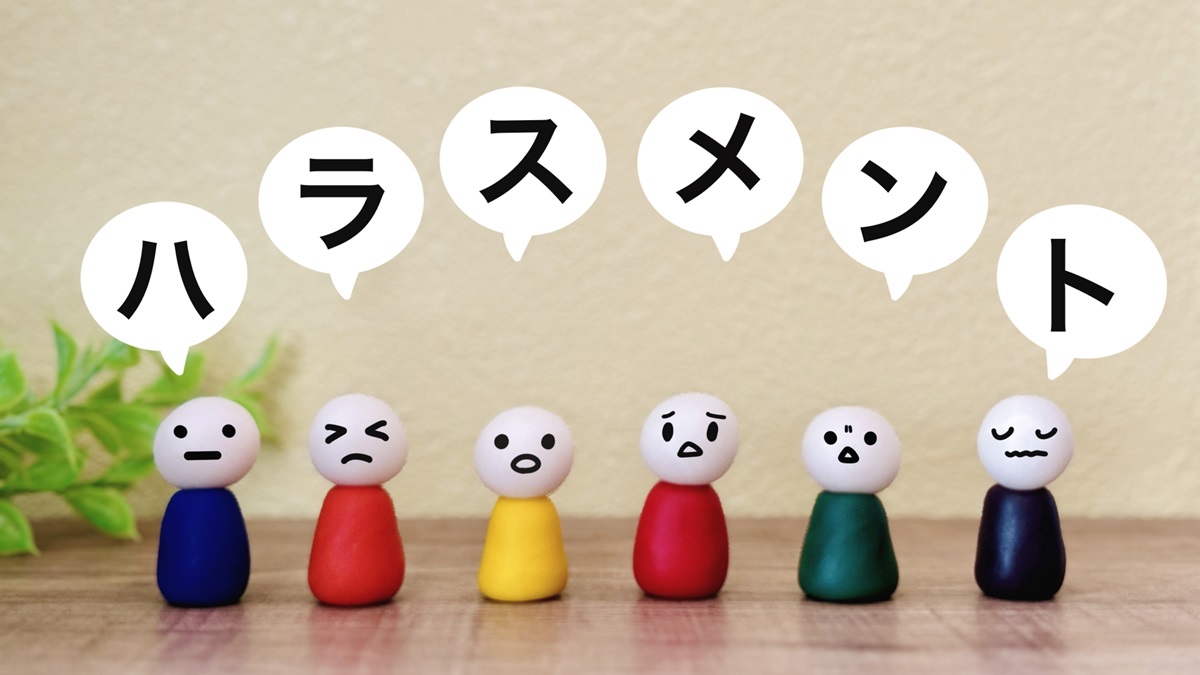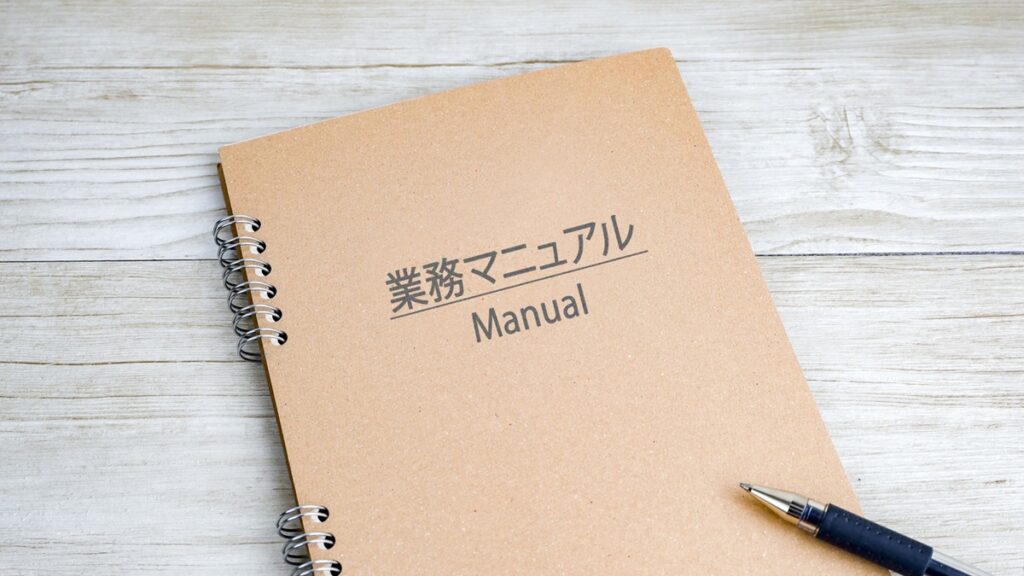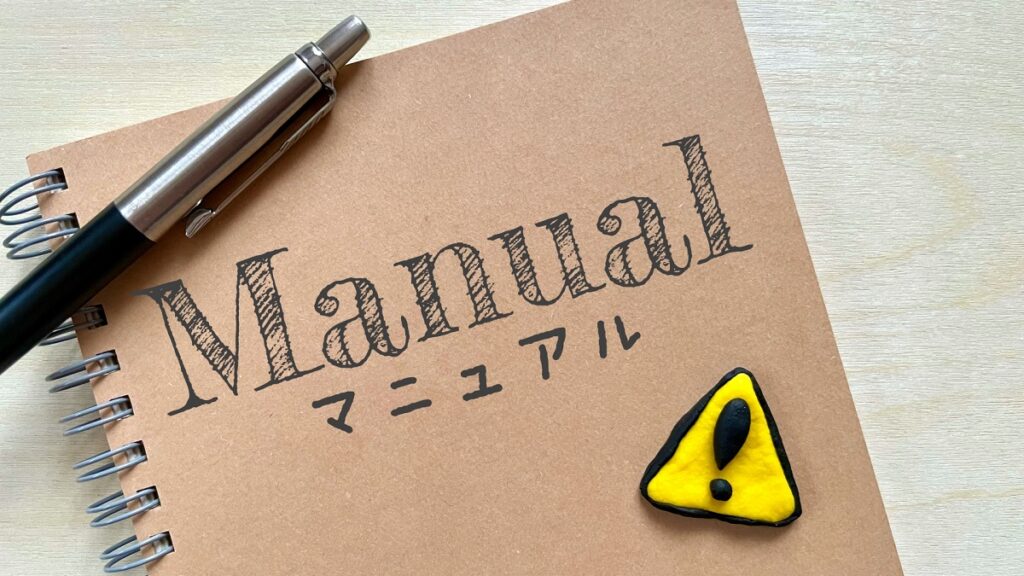ハラスメント防止指針の必要性
職場におけるハラスメント防止は、すべての事業者に求められる重要な課題です。
セクシャルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)、そして利用者やその家族からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント=カスハラ)は、職員の精神的な負担を増大させ、業務効率や職場環境を悪化させる大きな要因となっています。
これを受け、厚生労働省は「パワーハラスメント防止指針」を策定しました。この指針は、障害福祉サービス事業者が職場環境を改善し、全職員が安全に働ける環境を整備することを目的としています。背景には、「男女雇用機会均等法」第11条第1項や「労働施策総合推進法」第30条の2第1項があり、これらに基づき事業者の具体的な責務が定められています。
本記事では、この指針が求める具体的な取り組みや、事業者が行うべき実践方法について詳しく解説します。
【参考】基準の解釈通知 第3の3の(22) 一部抜粋
- 同条第4項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2第1項の規定に基づき、指定居宅介護事業者には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。
指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容及び指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。
なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。
- ア 指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容
指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18 年厚生労働省告示第615号)及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハラスメント指針」という。)において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。
- a 指定居宅介護事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
- b 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備と。相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知するこ
- a 指定居宅介護事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
- イ 指定居宅介護事業者が講じることが望ましい取組について
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
②被害者への配慮のているので参考にされたいための取組
(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)及び
③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されているので参考にされたい。
- ア 指定居宅介護事業者が講ずべき措置の具体的内容
具体的な対策 – 事業者が取るべき雇用管理上の措置
指定基準の解釈通知では、事業者が講じるべき具体的な雇用管理上の措置が示されています。そのポイントは以下の通りです。
- 方針の明確化と従業員への周知
指定居宅介護事業者は、職場におけるハラスメントの内容や「ハラスメントを行ってはならない」という方針を明確にし、従業員に周知・啓発する必要があります。この際、ポスターや社内文書、研修を活用して、全従業員に理解させることが重要です。 - 相談窓口の整備と対応体制の確立
相談や苦情を受け付ける窓口をあらかじめ設置し、その担当者を明確にして従業員に周知します。また、相談者が安心して話せる環境を整えると同時に、プライバシーの保護を徹底することが求められます。
これらの措置を通じて、職場での問題発生時に迅速かつ適切に対応する体制を整えることができます。
望ましい取り組み – カスタマーハラスメントへの対策
障害福祉業界では、利用者やその家族によるハラスメント(カスハラ)が職員のメンタルヘルスに深刻な影響を与えることがあります。この問題に対処するため、指針では事業者が行うべき望ましい取り組み例を示しています。
- 適切な相談体制の整備
カスハラに関する相談窓口を設置し、職員が気軽に相談できる環境を整えます。また、相談内容に応じて、適切な対応策を講じることが重要です。 - 被害者への配慮と支援
被害を受けた職員に対し、メンタルヘルスサポートや心身のケアを提供します。また、行為者に対しては複数人で対応する体制を作り、被害者が直接対面しなくて済む仕組みを導入することが有効です。 - 防止策の導入
マニュアルの作成や研修の実施を通じて、従業員がカスハラに対応するスキルを習得します。職場ごとの状況に応じた柔軟な取り組みが求められます。
\事業者必須!/
まとめ – 指針遵守がもたらす職場環境の向上
ハラスメント防止指針を作成し対応を実施することで、現場の職場環境は大きく改善されます。職員が安全かつ安心して働ける職場を構築することは、離職率の低下や業務効率の向上に直結します。また、これによりサービス利用者へのケアの質も向上します。
事業者が目指すべきは、法律を守ることに留まらず、職場全体の意識改革を促すことです。具体的な行動計画を策定し、継続的な取り組みを行うことで、全員が快適に働ける職場環境を実現しましょう。