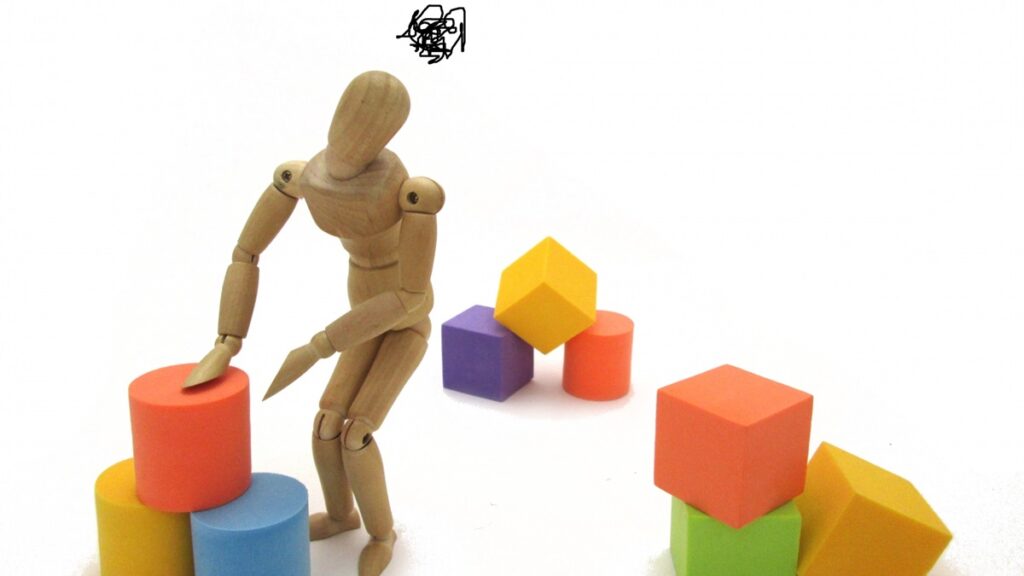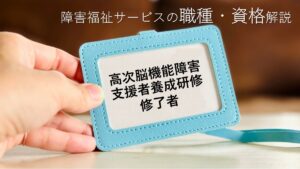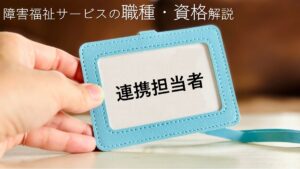「経口維持加算」の概要
「経口維持加算」とは、摂食機能障害や誤嚥のある方の経口摂取を支援するための障害福祉サービスの加算制度です。
医師や歯科医師の指示のもと、管理栄養士や看護師などが協力して栄養管理を行い、特別な食事計画を策定します。この制度により、入所者が安全で持続的に食事を摂取できる環境を整えることが目的です。
※令和6年4月1日現在
| (1)加算(Ⅰ) | 400単位/月 |
| (2)加算(Ⅱ) | 100単位/月 |
対象サービス
算定要件など
- 対象者の条件
- 経口維持計画の策定
- 継続的な栄養管理方法を示す計画を作成。
- 対象者や家族の同意が必須。
- 算定期間と管理体制
- 注意点
- 他の加算(栄養マネジメント加算など)との兼ね合いに注意。
- 算定できない場合の条件を確認。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
| (1)加算(Ⅰ) | 400単位/月 |
| (2)加算(Ⅱ) | 100単位/月 |
注1 (1)について
指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。
ただし、11の経口移行加算を算定している場合又は10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
注2 (2)について
注3
経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画に基づき管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
- 報酬告示第9の12の経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅰ))及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅱ))に係るものについては、次に掲げるアからエまでの通り、実施するものとすること。
- ア 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む。)ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。
ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ。)。
経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査)、「食物テスト(food test))、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。)、頸部聴診法等により誤嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。 - イ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること(ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。
また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
なお、指定施設入所支援においては、経口維持計画に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。 - ウ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。
「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。
経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた目から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 - エ 入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して180日を超えた場合でも、引き続き、
(ア) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ(喉頭侵入が認められる場合を含む。)継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合
(イ) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。
ただし、(ア)又は(イ)における医師又は歯科医師の指示は、概ね一月ごとに受けるものとすること。
- ア 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む。)ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。
参考:障発第1031001号
Q&A
-
【Q&A】水飲みテストとはどのようなもの?│R03,05,07.問8
-
【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが要件だが、食事の観察・会議に加わる歯科医師、歯科衛生士も協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7
-
【Q&A】「経口維持計画」の作成・栄養管理・支援期間が6月超の場合の医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は歯科医師である必要がある?│R03,05,07.問6
-
【Q&A】経口維持加算の歯科医師は、入所している歯科医師でなければいけない?│H24,03,30.問55
-
【Q&A】経口移行加算、経口維持加算を算定する場合、医師の診断が必要か?│H21,04,01.問11-6
関連記事
\事業者必須!/
まとめ
「経口維持加算」は、摂食機能障害や誤嚥を抱える入所者が安全に経口摂取を続けられるよう支援するための重要な制度です。
この制度を活用するには、対象者の診断条件を満たすこと、適切な経口維持計画を策定すること、そして関係職種が連携して支援体制を整えることが求められます。
適用条件や制限事項を十分に理解した上で、入所者のQOL向上に役立ててください。