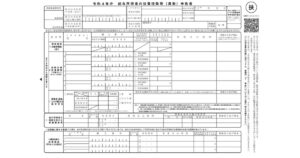従業員が退職する際の基本的な手続きについて、事業者側からの視点スムーズな流れを解説します。退職届の提出方法や期限、雇用保険や年金の手続きについて詳しく紹介します。
事前準備
従業員から退職の申し出があった際には、「退職届」を提出してもらいましょう。
Excelフォーマット:
その後、退職にあたっての詳細について協議しましょう。
- 今後について、転職するかしないか?
- 離職票は必要か?
- 退職後の各書類について会社から従業員に渡す予定など
- 住民税の残り期間についてどうするか
退職時に渡すもの
- 年金手帳
- 退職証明書(求めがあれば発行する。ハローワークで発行)
- 社会保険の資格喪失証明書(求めがあれば渡す。決まったフォーマットはない)
回収するもの
- 健康保険証
- 社員証、その他制服など貸与しているもの
退職後に悪用される事を未然に防止するため、場合もあるので、確実に回収しましょう。
※会社の従業員と見られる外形を備えていた場合、退職後であっても管理責任が問われる恐れがある
手続き
雇用保険の喪失手続き
「雇用保険被保険者資格喪失届」を作成し、管轄のハローワークで手続き
※資格喪失年月日:退職日(在籍の最終日)
健康保険・厚生年金の手続き
資格喪失届を日本年金機構に提出します。その場合、資格喪失日は退職日の翌日であることに注意してください。(例:2023年3月31日退職の場合⇒資格喪失日は2023年4月1日)
国民健康保険に加入するため、健康保険の「資格喪失証明等」が必要となった場合は、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を年金事務所又は広域事務センターに提出します。詳細は↓のリンクから日本年金機構のサイトをご確認ください。
住民税
転職以外で退職する場合、特別徴収で納付できなくなる未徴収をどうするかですが、退職日によって取り扱いがことなります。以下にまとめました。
- 退職日が1/1~4/30:会社が一括徴収しなければなりません。
- 退職日が5/1~5/31:最後の給与から特別徴収されます。
- 退職日が6/1~12/31:退職者の意思で一括徴収か普通徴収への切替かを選択できます。
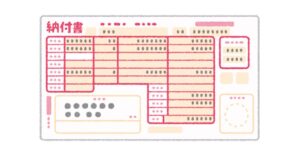
トラブルから退職となった場合の注意点
従業員とは円満な関係が望ましいですが、そうならない場合もあります。意見の食い違いなので従業員が退職する場合、会社を守るために気を付けなければならないことがあります。
従業員からの自主退職の場合、退職願い(届)をもらう。退職した従業員からあとで不当解雇と訴えられる場合があります。その場合にそなえて退職願い(届)を必ず書いてもらう。
事前に労基署に話をして、問題となりそうなことがあったら事前に確認しておいたほうがいいです。労基署は中立な立場ですので事業者側の話も聞いてくれます。
保険会社から聞いた話ですが、かなりの期間がたってから、精神疾患を患いその後の再就職に支障をきたした等の理由で訴えられる事例があるようです。可能であれば退職前に診察してもらい診断書の控えを保管しておいたほうがいいかもしれません。