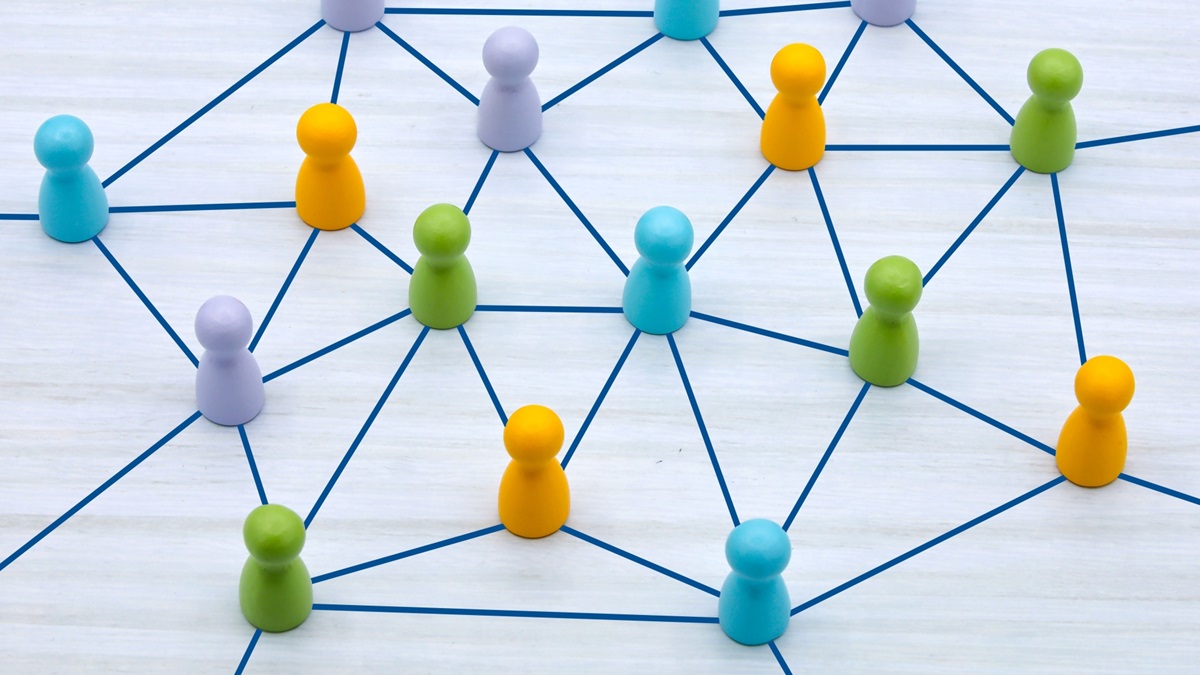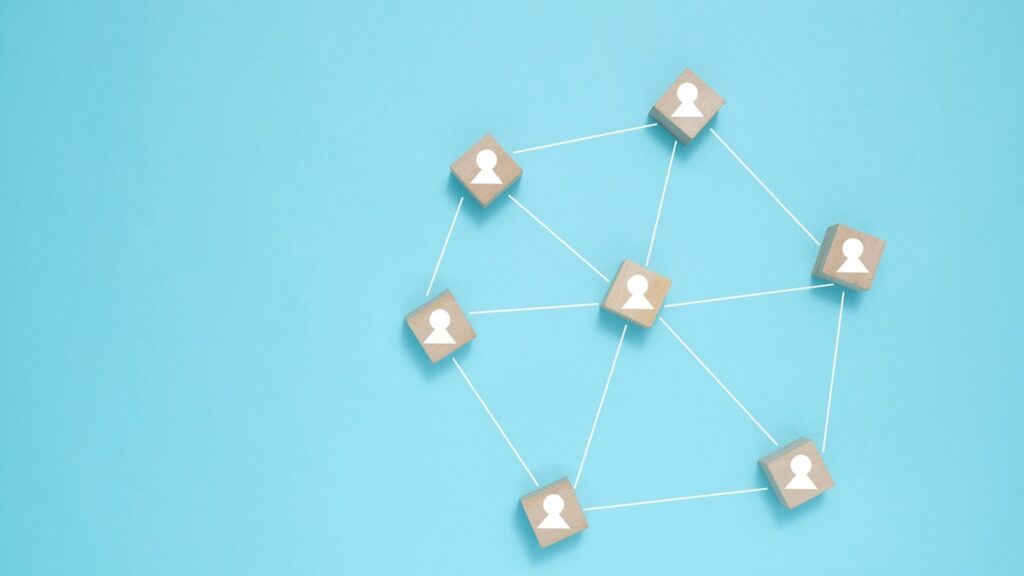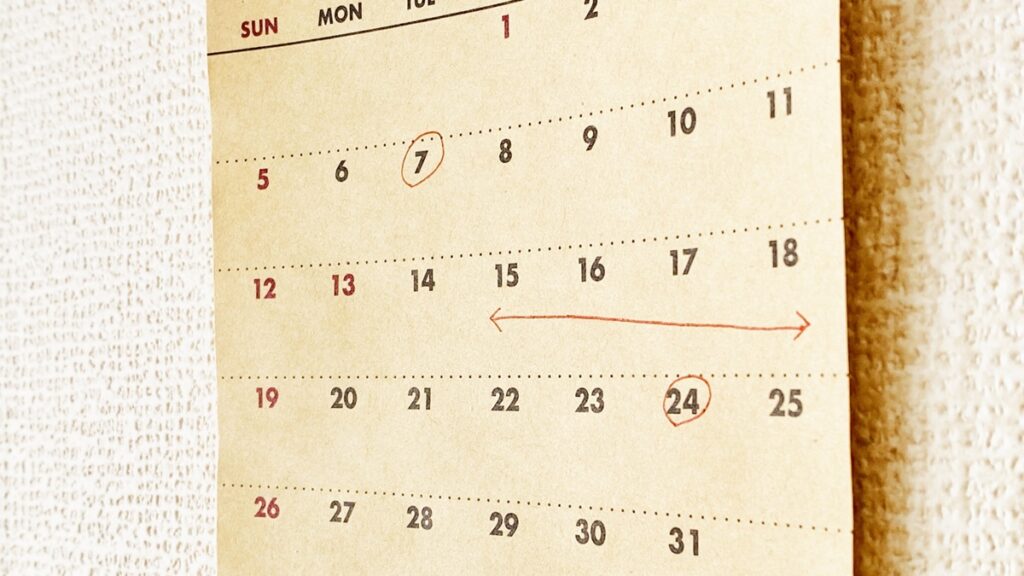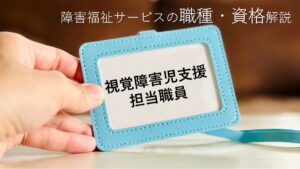「中核機能強化加算」の概要
中核機能強化加算とは?地域支援の中心を担う加算制度
中核機能強化加算は、障害福祉サービスにおいて地域全体の支援体制を強化するための重要な加算制度です。この制度は、自治体や地域の関係機関と連携し、障害児とその家族に包括的な支援を提供する事業所に対して適用されます。特に、専門的な人材を配置し、幅広いニーズに応える体制を整える事業所が対象です。
事業所がこの加算を取得することで、サービスの質を向上させるための費用が確保しやすくなり、地域の障害児支援をリードする存在となります。また、加算を活用した取り組みは、個別支援の充実だけでなく、地域全体の福祉環境の改善にもつながるため、多くの事業所で注目されています。
対象サービス
算定要件など
- 市町村からの認定:
事業所が中核的な役割を担う施設として市町村に認定されることが必須です。事前協議を行い、認定を受ける必要があります。 - 地域との連携体制:
市町村や地域の福祉関係機関と連携し、定期的に情報共有や協議を行う仕組みを整えること。 - 専門人材の配置:
理学療法士や作業療法士、心理担当職員など、資格と実務経験を有する専門人材を常勤で配置することが求められます。 - 多様な支援の提供:
未就学児から学齢期の児童まで、幅広い障害特性に応じた支援体制を確立すること。保育所訪問や学齢児支援も含みます。 - 包括的な相談窓口の設置:
障害児やその家族が利用できる相談窓口を設置し、早期支援を提供する体制を確保すること。 - 情報公開と評価:
支援の取り組み状況や地域の福祉体制を定期的に公開し、外部評価を受けることで透明性を高める。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)が、指定児童発達支援を行った場合にあっては、中核機能強化加算として、当該基準に掲げる区分に従い、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 中核機能強化加算(Ⅰ)
| 利用定員 | 単位 |
| (一)30人以下 | 155単位 |
| (二)31~40人 | 133単位 |
| (三)41~50人 | 103単位 |
| (四)51~60人 | 85単位 |
| (五)61~70人 | 73単位 |
| (六)71~80人 | 63単位 |
| (七)81人~ | 55単位 |
ロ 中核機能強化加算(Ⅱ)
| 利用定員 | 単位 |
| (一)30人以下 | 124単位 |
| (二)31~40人 | 106単位 |
| (三)41~50人 | 82単位 |
| (四)51~60人 | 68単位 |
| (五)61~70人 | 58単位 |
| (六)71~80人 | 50単位 |
| (七)81人~ | 44単位 |
ハ 中核機能強化加算(Ⅲ)
| 利用定員 | 単位 |
| (一)30人以下 | 62単位 |
| (二)31~40人 | 53単位 |
| (三)41~50人 | 41単位 |
| (四)51~60人 | 34単位 |
| (五)61~70人 | 29単位 |
| (六)71~80人 | 25単位 |
| (七)81人~ | 22単位 |
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
留意事項
通所報酬告示第1の注7の中核機能強化加算については、障害児とその家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の障害児支援体制の充実強化を図るため、市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所、保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、障害児とその家族に対する専門的な支援及び包括的な支援の提供に取り組んだ場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 中核機能強化加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までの算定に当たっては、基本要件として、以下のアからケまでに掲げるいずれの要件も満たすこと。
- ア 市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援センターとして位置付けられていること。
具体的には、所在する市町村と事前協議を行ったうえで、当該加算の要件を満たすもの及び中核的機関として位置付けられているものと市町村が認めていること。 - イ 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保していること。
具体的には、市町村と定期的に情報共有の機会を設けることや地域の協議会(こどもの専門部会を含む)へ参画する等の取組を行っていること。地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を算定する事業所が複数ある場合には、市町村及びこれらの事業所間で日常的な相互連携を図ること。 - ウ 未就学から学齢期まで、幅広い発達段階及び多様な障害特性に応じた専門的な発達支援及び家族支援を提供する体制を確保していること。
具体的には、指定放課後等デイサービスの指定を有しこれを実施することや、保育所等訪問支援等により学齢期の児童への支援を行う等の取組を行っていること。 - エ 地域の障害児通所事業所との連携体制を確保していること。
具体的には、地域の障害児通所支援事業所と定期的に情報共有の機会を設けることや、児童発達支援センターの有する知識・経験に基づき地域の障害児通所支援事業所に対して研修会の開催や助言・援助を行う等の取組を行っていること。 - オ インクルージョンの推進体制を確保していること。
具体的には、指定保育所等訪問支援の指定を有しこれを実施することや、地域の保育所等に対して助言援助等の支援を行う等、障害児の併行通園や保育所等への移行等を推進する取組を行っていること。 - カ 発達支援に関する入口としての相談機能を果たす体制を確保していること。
具体的には、指定障害児相談支援を有しこれを実施すること、市町村から委託相談支援事業を受託すること、市町村が行う発達支援の入口の相談と日常的な連携を図ること等、地域の多様な障害児及び家族に対し早期の相談支援を提供する取組を行っていること。 - キ 地域の障害児に対する支援体制の状況及びイからカまでの取組の実施状況を年に1回以上公表していること。
インターネット等を活用し、広く公表すること。なお、地域の障害児に対する支援体制の状況については、市町村及び地域に中核機能強化加算又は中核機能強化事業所加算を算定する事業所が複数ある場合にあっては他の加算取得事業所との連携により、共同で作成・公表すること。 - ク 自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね年に1回以上受けていること。
具体的には、運営基準に定められる自己評価を実施するに当たり、自治体職員、利用児童や家族の代表、当事者団体、地域の障害児通所支援事業所等の第三者の同席を求め、客観的な意見を踏まえて自己評価を行っていること。
第三者評価等、外部の評価機関による外部評価を受審している場合は本要件を満たすものとする。 - ケ 児童発達支援センターの従業者に対する年間の研修計画を作成し、当該計画に従い、年に1回以上研修を実施していること。
この場合において、専門機関や専門家等による研修の実施や、外部研修への参加を進めるなど、従業者の専門性の向上に努めること。
なお、運営基準に定められている身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修等のみの実施の場合は本要件を満たさないものとする。
- ア 市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援センターとして位置付けられていること。
- 通所給付費等単位数表第1の1の注7のイの中核機能強化加算(Ⅰ)の算定にあたっては、❶の基本要件及び以下のアからウまでに掲げるいずれの要件も満たすこと。
- ア 主として障害児及びその家族等に対する包括的な支援の推進及び地域支援を行う中核機能強化職員として、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算又は専門的支援体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、主として❶のイ、エ及びオの体制確保について取り組む専門人材を常勤専任で1以上配置し、これらの取組を行っていること。
中核機能強化職員として配置する専門人材は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指導員又は心理担当職員であって、資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 - イ 主として専門的な発達支援及び相談支援を行う上で中心となる中核機能強化職員として、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算又は専門支援体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。また、アの専門人材を含む)に加え、主として❶のウ及びカの体制確保について取り組む専門人材を常勤専任で1以上配置し、当該取組を行っていること。中核機能強化職員として配置する専門人材の要件は、アと同様であること。
- ウ 多職種連携が可能な体制の下で、幅広い発達段階や多様な障害特性及び家族支援に対応するための専門的な支援の提供を行うこと。
具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士及び児童指導員を全て配置し、これらの者が連携して障害児通所支援が行われていること。
保育士及び児童指導員は、3年以上障害児通所支援又は障害児入所支援の業務に従事した経験を有する者であること。当該経験は、資格取得又は当該職務として配置された以後の経験に限らないものとする。
これらの配置に当たっては、指定通所基準により配置すべき従業者、児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算により加配された者、ア又はイの中核機能強化職員の配置によることができる。また、配置は常勤換算による配置を求めるが、配置すべき者に係る職種のうち2職種までは、常勤換算でない配置によることも可能とする。さらに、同一の者が複数の職種を有している場合には、常勤換算による配置である場合に限り、2職種までは配置したものと評価することを可能とする。
例:同一法人内の他の施設に勤務する専門職の活用や理学療法士及び言語聴覚士を非常勤で自事業所に勤務させる体制を確保する場合は、これらの職種について配置したものと認められる。
- ア 主として障害児及びその家族等に対する包括的な支援の推進及び地域支援を行う中核機能強化職員として、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算又は専門的支援体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、主として❶のイ、エ及びオの体制確保について取り組む専門人材を常勤専任で1以上配置し、これらの取組を行っていること。
- 通所給付費等単位数表第1の1の注7のロの中核機能強化加算(Ⅱ)の算定にあたっては、❶の基本要件並びに❷のア及びイに掲げるいずれの要件も満たすこと。
- 通所給付費等単位数表第1の1の注7のハの中核機能強化加算(Ⅲ)の算定にあたっては、❶基本要件及び❷のア又はイに掲げるいずれの要件も満たすこと。
- 中核機能強化職員については、支援を提供する時間帯は事業所で支援に当たることを基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたることができること。ただし、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務はできないこと。
- 中核機能強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)により、2以上の中核機能強化職員を配置している場合にあっては、❷のア及びイに規定する業務の適切な実施の確保に留意した上で、当該2以上の中核機能強化職員が連携して❷のア及びイに規定する業務を一体的に実施することとしても差し支えない。
また、中核機能強化加算(Ⅲ)により、❷のア又はイのいずれかの業務を主として実施する1の中核機能強化職員を配置している場合にあっては、残りのア又はイのいずれかの業務についても、可能な限りあわせて取り組むよう努めること。
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
関連記事
\事業者必須!/
まとめ
中核機能強化加算は、障害児支援の質を向上させるための重要な仕組みです。この加算を取得するためには、市町村の認定や専門人材の配置、地域との連携体制の構築など多岐にわたる要件を満たす必要があります。しかし、これらを整えることで事業所の支援力が向上し、地域全体の障害児支援体制がより充実します。
障害児とその家族に対する支援をより専門的かつ包括的に行うためには、この加算制度を効果的に活用することが鍵です。地域全体で障害福祉の未来を築くためにも、中核機能強化加算の活用を検討してはいかがでしょうか?