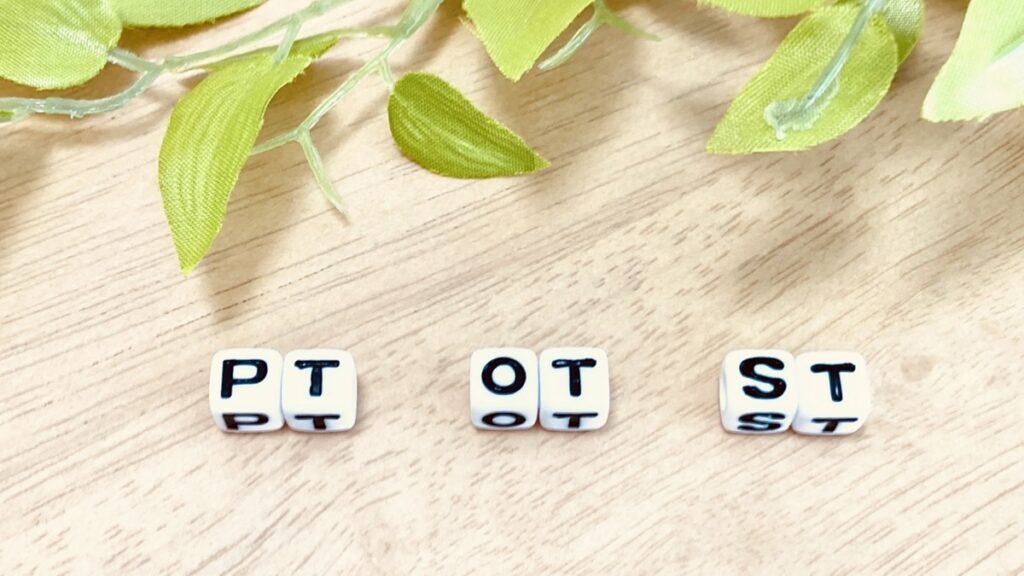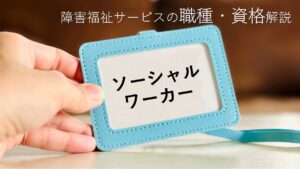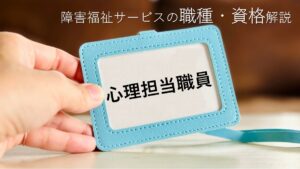「移行支援関係機関連携加算」の概要
移行支援関係機関連携加算は、障害福祉サービスにおける支援計画作成・更新時に、関係機関と協力して支援内容を調整することで算定される加算です。
具体的には、障害児入所施設が移行支援計画を作成または変更する際、都道府県や市町村、基幹相談支援センターなどが会議に参加し、専門的な見地から支援計画の内容について意見交換を行います。
これにより、障害児が自立した社会生活に移行するための支援がより効果的に行われることを目的としています。
※令和6年4月1日現在
| (月1回を限度として)250単位/回 |
対象サービス
算定要件など
- 加算対象施設と対象者
対象となる施設は指定福祉型障害児入所施設で、支援計画の作成や更新時に関係機関との調整が求められます。15歳未満の障害児も支援計画が必要と認められれば加算の対象となります。 - 会議参加者
基本的に、都道府県、市町村、基幹相談支援センター、教育機関が参加します。また、障害児本人や保護者、医療機関、日中活動サービスの関係者などが必要に応じて参加します。 - 会議内容
会議では、移行支援計画の作成・更新の過程で意見交換を行い、支援計画に反映させるための調整を行います。会議内容は記録し、後日反映させることが求められます。 - 情報共有と日常的な連携
支援機関は日常的に情報を共有し、障害児や保護者の意向に基づき支援内容を調整します。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
| (月1回を限度として)250単位/回 |
注 指定福祉型障害児入所施設において、移行支援計画(指定入所基準第3条第1項に規定する移行支援計画をいう。以下同じ。)の作成または変更に当たって、関係者(都道府県、市町村及び教育機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は障害者総合支援法第77条の2に規定する基幹相談支援センターその他の障害児の自立した日常生活又は社会生活への移行に関係する者をいう。以下この注及び第2の4の2の注において同じ。)により構成される会議を開催し、当該移行支援計画に係る障害児への移行支援について、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め、必要な情報の共有及び当該障害児の移行に係る連携調整を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。
留意事項
入所報酬告示第1の6の2の移行支援関係機関連携加算は、指定福祉型障害児入所施設が障害児の移行支援計画を作成又は更新する際に、関係者が参画する移行支援関係機関連携会議(以下この⑬の3において単に「会議」という。)を開催し、当該障害児の移行支援に関して連携調整を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、当該障害児が15歳未満であっても、移行支援計画の作成が必要と認められる場合は、当該加算の対象として差し支えない。
- 会議には、障害児の入所給付決定を行った都道府県等(指定都市を含む。)、移行予定先の(未定の場合には入所給付決定保護者の居住地又は指定福祉型障害児入所施設の所在地の)市町村及び基幹相談支援センター、障害児が所属する教育機関の出席を基本とすること。
基幹相談支援センターが障害児の移行予定先や入所給付決定保護者の居住地又は指定福祉型障害児入所施設の所在地の市町村に設置されていない場合は、当該市町村の指定特定相談支援事業所が出席すること。
また、これらの参加者のほか、必要に応じて、障害児本人及びその家族、児童相談所、移行予定先の日中活動サービスや居住先施設の関係者、医療機関等の関係者その他の障害児の移行支援に関係する者の参加を求めること。
なお、会議は、テレビ電話装置等を活用した開催としても差し支えないが、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。
また、障害児の移行支援に関する関係機関の連携調整を評価する当該加算の主旨を踏まえると、会議は全ての関係者が出席することを基本とするが、やむを得ず欠席が生じる場合には、当該欠席する関係機関と事前及び事後に移行支援及び会議に関する情報共有及び連携調整を行うこと。 - 会議においては、当該指定福祉型障害児入所施設の児童発達支援管理責任者又はソーシャルワーカーが、入所児童の状況、移行支援計画の原案の内容及び実施状況について説明を行うとともに、参加者に対して、専門的な見地からの意見を求め、移行支援計画の作成又は変更その他必要な便宜の提供について検討を行うこと。
会議を行った場合は、参加者、開催日時、会議の要旨及び移行支援計画に反映させるべき内容等を記録すること。 - 会議における検討を踏まえて、移行支援計画の作成又は見直しを行うこと。
作成又は見直しに当たっては、関係者との連携方法等を具体的に記載すること。 - 会議に加えて、参加者との日常的な連携調整の体制を整えること。
日常的な連携調整においては、当該障害児や保護者の意向、支援内容、移行に向けた課題などについて適切に情報共有を行うこと。 - ❶から❷までに関わらず、都道府県又は指定都市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の19第4項に規定する協議の場を設け、当該協議の場に指定福祉型障害児入所施設及び関係機関が参加し、❶から❹までに掲げる取組と同等の取組を行った場合には、当該加算を算定することとして差し支えないこと。
Q&A
記事が見つかりませんでした。
関連記事
\事業者必須!/
まとめ
「移行支援関係機関連携加算」は、障害福祉事業において重要な役割を果たしています。障害児の移行支援計画を作成・更新する際に関係機関が連携し、情報を共有することで、支援計画がより実効性のあるものとなります。
加算対象となるのは障害児入所施設で、会議には都道府県、市町村、基幹相談支援センター、教育機関などが参加します。これにより、障害児の自立した社会生活への移行支援が円滑に行われ、より質の高い支援が提供されることが期待されています。