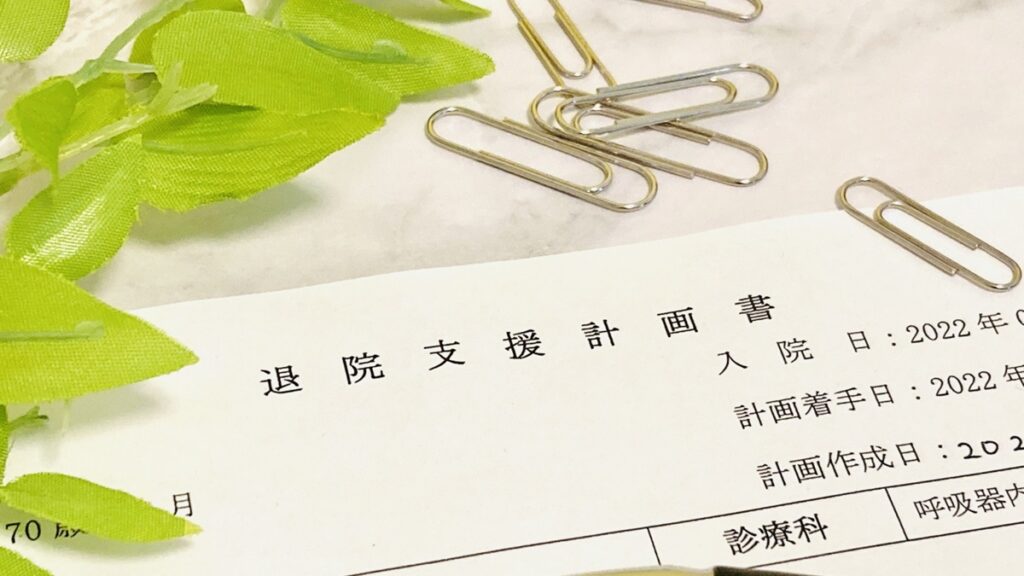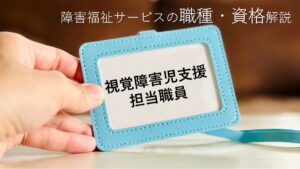「食事提供加算」の概要
障害福祉サービス事業における「食事提供加算」とは、障害児の健全な発育を支援するため、児童発達支援センターなどが提供する食事に対して加算される報酬項目です。
この制度は、特に低所得世帯や中所得世帯の障害児を対象としており、施設内の調理室で調理された食事を提供することが条件です。
栄養面や特性に配慮した献立や食事提供を行うことで、保護者の負担を軽減し、障害児の成長を支えることを目的としています。
※令和6年4月1日現在
| イ 食事提供加算(Ⅰ) | 30単位/日 |
| ロ 食事提供加算(Ⅱ) | 40単位/日 |
対象サービス
算定要件など
- 施設内調理の厳守:
施設内の調理室を使用し、自ら調理した食事を提供することが必須。 - 栄養士・管理栄養士の指導:
栄養士または管理栄養士による献立確認と指導が求められます。 - 障害特性に応じた対応:
障害児の年齢や特性に配慮し、適切な食事を提供すること。 - 記録と定期的な確認:
食事摂取状況や身体成長を記録・確認すること。 - 保護者との関係:
- 加算Ⅰ:家族等から相談について対応と記録
- 加算Ⅱ:保護者への食事や栄養に関する情報提供を行う研修会を年1回以上開催。
- 複数回分の算定不可:
複数回分の加算は認められず、1日1回限りの適用となる。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
| イ 食事提供加算(Ⅰ) | 30単位/日 |
| ロ 食事提供加算(Ⅱ) | 40単位/日 |
注 イ又はロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号に掲げる通所給付決定保護者にあっては、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに該当する場合における当該中初給付決定保護者、同上第6号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)に係る障害児に対して、児童発達支援センターの調理室において調理された食事を提供するものとして都道府県知事に届け出た児童発達支援センターにおいて、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する食事提供を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
留意事項
通所報酬告示第1の3の食事提供加算については、低所得者・中所得者世帯の障害児に対して、令和9年3月31日までの間、障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 食事提供加算(Ⅰ)の算定については、以下のいずれも満たすこと。
- ア 児童発達支援センターの調理室において調理された食事を提供していること。
原則として当該施設が自ら調理し、提供することとするが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。
ただし、当該調理委託が行えるのは施設内の調理室を使用して調理させる場合に限り、施設外で調理し、搬入する方法は認められないものであること。
また、出前の方法や市販の弁当を購入して、障害児に提供するような方法も認められない。 - イ 栄養士が食事の提供に係る献立を確認するとともに、障害児が健全に発育できるよう、障害児ごとに配慮すべき事項に応じて適切かつ効果的な食事提供の支援及び助言を行うこと。次のウからキまでの取組についても、当該栄養士による指導及び助言の下で行うこと。
この場合において、栄養士は従業者である他、同一法人内に勤務する栄養士の活用、保健所や栄養ケアステーション等の外部機関の栄養士との連携、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託している場合には、委託先の栄養士による指導・助言の下で行うこととしても差し支えないこと。 - ウ 障害児の障害特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況その他の障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた適切な食事提供を行うこと。
- エ 提供した食事について、障害児ごとの摂取状況を把握し、記録を行うこと。
- オ 定期的に障害児の身体の成長状況(身長・体重等)を把握し、記録を行うこと。
- カ 食に関する体験の提供その他の食育の推進に関する取組を計画的に実施していること。例えば、行事食の提供や調理実習等を年間の予定に組み込み、定期的に実施することが考えられる。
- キ 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応すること。
相談等の対応を行った場合は、当該対応を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。
- ア 児童発達支援センターの調理室において調理された食事を提供していること。
- 食事提供加算(Ⅱ)の算定については、以下のいずれも満たすこと。
- ア ❶のアからキまでに規定を準用する。
この場合において、❶のイの「栄養士」を「管理栄養士」と読み替えて適用すること。 - イ 年に1回以上、障害児の家族等に対して、食事や栄養に関する研修会等を開催し、食事に関する情報提供を行うこと。
- ア ❶のアからキまでに規定を準用する。
- 栄養士又は管理栄養士による献立の確認や助言・指導については、事業所に栄養士が配置されている場合であっても、外部機関等との連携により、管理栄養士等と連携を図りながら取組等を行った場合には、食事提供加算(Ⅱ)の算定ができるものとする。
- 1日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについては、当該加算がその食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。
ただし、特定費用としての食材料費については、複数食分を通所給付決定保護者から徴収して差し支えないものである。
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
記事が見つかりませんでした。
関連記事
\事業者必須!/
障害福祉サービス事業における「食事提供加算」は、障害児の栄養面や成長を支えるための重要な仕組みです。児童発達支援センターなどの施設が、栄養士や管理栄養士の指導のもと、適切な食事提供を行うことで加算が適用されます。
施設内調理や食事摂取状況の記録、さらには保護者への研修会開催など多岐にわたる要件がありますが、これらを通じて障害児とその家族を支援する意義深い制度です。この制度の正しい理解と活用は、障害福祉の質を高める大きな一歩となるでしょう。