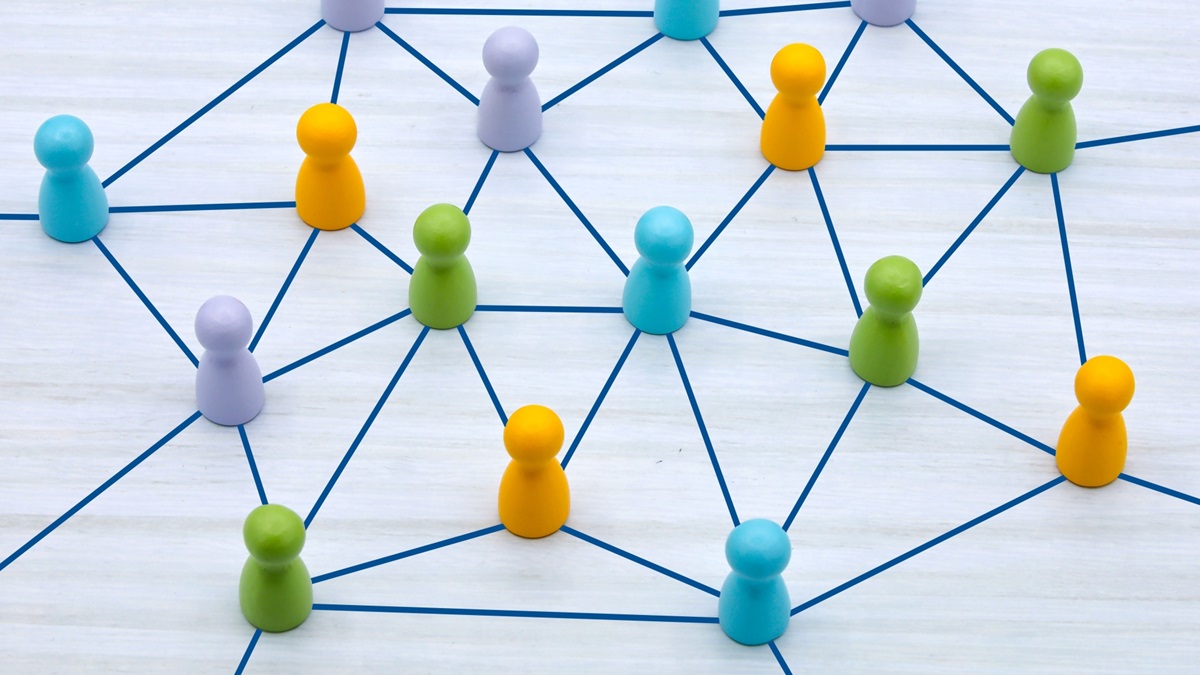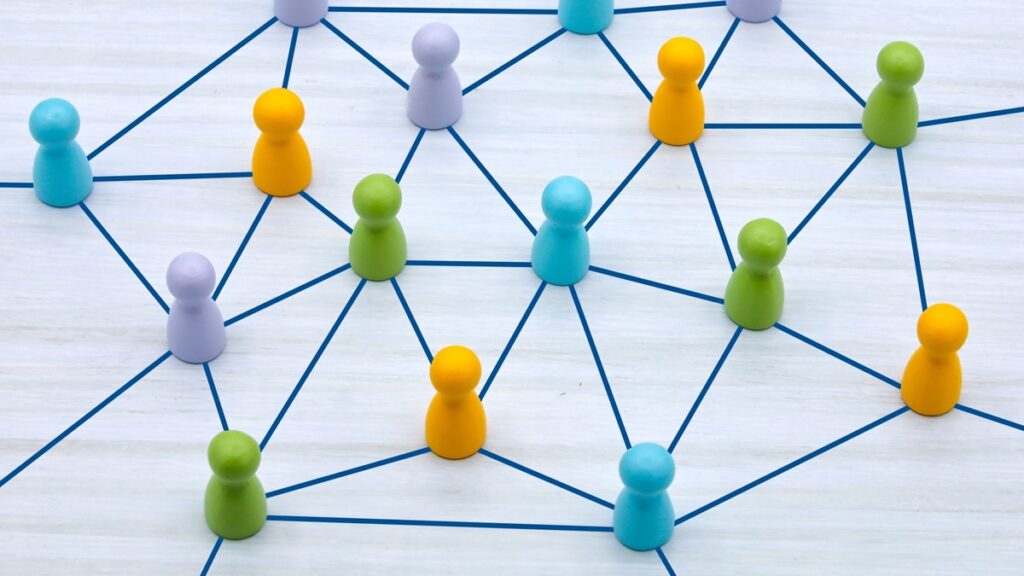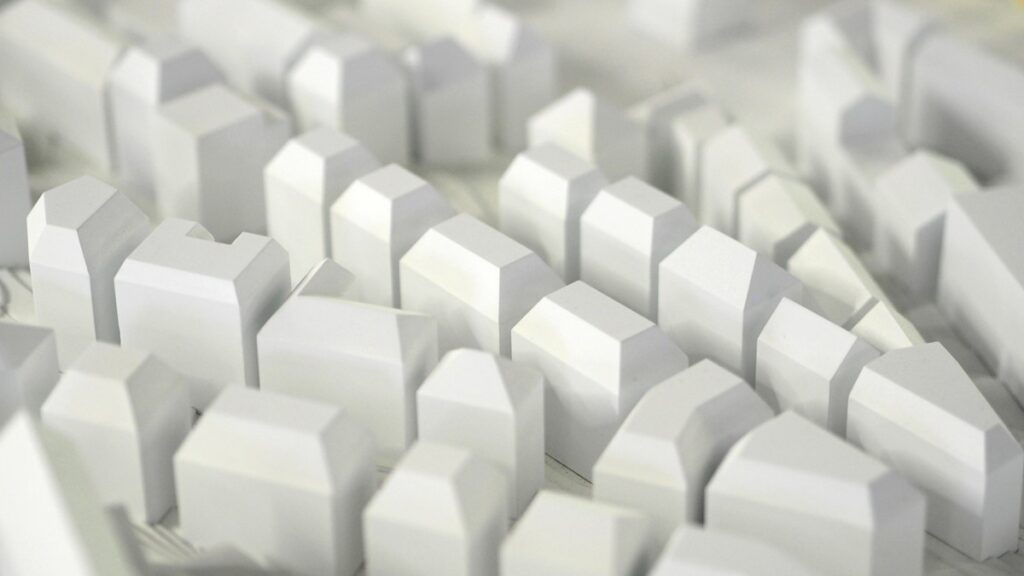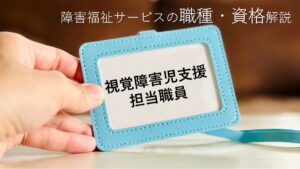「事業所間連携加算」の概要
事業所間連携加算は、複数の指定児童発達支援事業所を利用する障害児に対して、事業所同士が連携して適切な支援を提供した場合に加算される報酬制度です。
この制度は、セルフプランの利用者を主な対象とし、障害児が一貫した支援を受けられるようにすることを目的としています。事業所間の情報共有や会議の開催を通じて、障害児の発達や生活環境の改善に寄与します。
※令和6年4月1日現在
| イ 事業所間連携加算(Ⅰ) | 500単位/回 (月1回を限度) |
| ロ 事業所間連携加算(Ⅱ) | 150単位/日 (月1回を限度) |
対象サービス
算定要件など
■コア連携事業所の役割
- 市町村から依頼を受け、中心的な役割を担う。
- 保護者の同意を得たうえで、他事業所と支援状況や計画を共有。
- 必要に応じて会議を開催し、テレビ電話の活用も可能。
■他の事業所の要件
- コア連携事業所が開催する会議に参加し、情報共有を行う。
- 会議への参加が難しい場合は、事前・事後に情報を共有し、計画の調整を行う。
■加算が適用されない場合
- 加算対象児が利用する全ての事業所が同一法人によって運営されている場合。
- この場合でも情報共有や連携の努力が求められる。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
| イ 事業所間連携加算(Ⅰ) | 500単位/回 (月1回を限度) |
| ロ 事業所間連携加算(Ⅱ) | 150単位/日 (月1回を限度) |
注 指定児童発達支援事業所等において、法第21条の5の7第5項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案を市町村に提出した通所給付決定保護者に係る障害児が、複数の指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を受けている場合であって、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する事業所間の連携を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
留意事項
通所報酬告示第1の12の3の事業所間連携加算は、障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、事業所間で連携し、児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 事業所間連携加算の対象となる障害児
市町村における支給決定において、指定障害児相談支援事業者が作成する計画案に代えて、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成するセルフプランが提出されている障害児であって、複数の指定児童発達支援事業所等から、継続的に指定児童発達支援の提供を受ける障害児であること(以下この⑮の3において「加算対象児」という。)。 - 通所報酬告示第1の12の3のイの事業所間連携加算
(Ⅰ)は、連携・取組の中心となるコア連携事業所を評価するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- ア 市町村から、加算対象児の支援について適切なコーディネートを進める中核となるコア連携事業所として、事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた指定児童発達支援事業所等であること。
- イ コア連携事業所として、あらかじめ保護者の同意を得た上で、加算対象児が利用する他の指定児童発達支援事業所等との間で、加算対象児に係る支援の実施状況、心身の状況、生活環境等の情報及び加算対象児の通所支援計画の共有並びに支援の連携を目的とした会議を開催し、情報共有及び連携を図ること。
会議は、テレビ電話装置等を活用した開催としても差し支えない。また、会議は加算対象児が利用する全ての事業所が出席することを基本とするが、やむを得ず欠席が生じる場合にも、本加算の算定を可能とする。
この場合であっても、当該欠席する事業所と事前及び事後に加算対象児及び会議に関する情報共有及び連絡調整を行うよう努めること。 - ウ 会議の内容及び整理された加算対象児の状況や支援に関する要点について、記録を行うとともに、他の事業所、市町村、加算対象児の保護者に共有すること。
市町村に対しては、あわせて、加算対象児に係る各事業所の通所支援計画を共有すること。また、障害児及び保護者の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必要性の要否について報告すること。 - エ 加算対象児の保護者に対して、ウで整理された情報を踏まえた相談援助を行うこと。
当該相談援助については、家庭連携加算の算定が可能であること。 - オ ウで整理された情報について、事業所の従業者に情報共有を行い、当該情報を踏まえた支援を行うとともに、必要に応じて通所支援計画を見直すこと。
- ア 市町村から、加算対象児の支援について適切なコーディネートを進める中核となるコア連携事業所として、事業所間の連携を実施するよう依頼を受けた指定児童発達支援事業所等であること。
- 通所報酬告示第1の12の3のロの事業所間連携加算(Ⅱ)は、コア連携事業所以外の事業所を評価するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- ア 加算対象児が利用するコア連携事業所以外の指定児童発達支援事業所等であること。
- イ コア連携事業所が開催する会議に参加し、必要な情報共有及び連携を行うとともに、通所支援計画をコア連携事業所に共有すること。
なお、会議への参加を基本とするが、やむを得ず出席できない場合であって、会議の前後に個別にコア連携事業所と情報共有等を行い連携を図るとともに、通所支援計画の共有を行った場合には本加算の算定を可能とする。 - ウ ❷のウでコア連携事業所により整理・共有された情報について、事業所の従業者に情報共有を行い、当該情報を踏まえた支援を行うとともに、必要に応じて通所支援計画を見直すこと。
- ア 加算対象児が利用するコア連携事業所以外の指定児童発達支援事業所等であること。
- 本加算は、セルフプランの場合に適切な支援のコーディネートを図るためのものであることから、障害児相談支援におけるモニタリングと同様の頻度(概ね6月に1回以上)で取組が行われることが望ましい。
また、コア連携事業所において、加算対象児の変化が著しい場合など取組の頻度を高める必要があると判断された場合には、適切なタイミングで取組を実施すること。
また、加算対象児が利用する事業所においては、会議の実施月以外においても、日常的な連絡調整に努めること。 - 加算対象児が利用する事業所の全てが同一法人により運営される場合には、本加算は算定されない。
この場合であっても、加算対象児の状況や支援に関する情報共有を行い、相互の支援において連携を図ることが求められる。
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
記事が見つかりませんでした。
関連記事
\事業者必須!/
まとめ
事業所間連携加算は、障害児が複数の支援事業所を利用する場合に、支援の一貫性を確保するための重要な仕組みです。セルフプランを利用する障害児が主な対象で、コア連携事業所が中心的な役割を果たします。
連携を通じて適切な支援を提供し、障害児とその家庭をサポートすることが加算の目的です。本制度の適用要件を理解し、正しい運用を行うことで、より質の高い障害福祉サービスを実現できるでしょう。