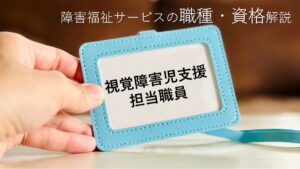障害福祉事業の「関係機関連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次
「関係機関連携加算」の概要
効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。
「関係機関連携加算」は、障害福祉サービス事業者が保育所、児童相談所、医療機関などの関係機関と連携を図り、障害児の支援環境を整えるための加算制度です。この制度の目的は、障害児が心身や生活環境に合わせた最適な支援を受けられるよう、関係機関と情報共有や調整を行うことです。
対象サービス
算定要件など – 児童発達支援・保育所等デイサービス
- (Ⅰ)関係機関との連携:
支援計画の作成・見直しに関する会議を開催。
- (Ⅱ)心身や生活状況の情報共有:
定期的な情報共有のための会議を開催または参加。
- (Ⅲ)児童相談所等との調整:
医療機関などの情報共有のための会議を開催または参加。
- (Ⅳ)就学や就職時の支援:
ライフステージ移行時の会議を開催または参加。
算定要件など – 保育所等訪問支援
会議の開催又は参加
- 通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童相談所等関係機関と情報共有のための会議を開催する、または会議に参加し、情報共有や連絡調整を行う。(テレビ電話装置活用可)
日常的な連絡調整
- 会議の開催にとどまらず、児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
記録の作成
- 会議または連絡調整を行った際には、以下の内容を記録する:
支援計画の見直し
- 会議結果や連絡調整を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直し、関係機関と連携した支援を提供。
- 訪問先施設を含めた連携を意識して取り組むこと。
多機能型事業所での取扱い
個別サポート加算との重複制限
- 加算対象児童が「個別サポート加算(Ⅱ)」を算定している場合、同加算における児童相談所等との情報連携に対しては本加算を算定しない。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
児童発達支援
| イ 関係機関連携加算(Ⅰ) | 250単位/回
(月1回を限度) |
| ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) | 200単位/回
(月1回を限度) |
| ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度) | 150単位/回
(月1回を限度) |
| ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度) | 200単位/回
(月1回を限度) |
注1 イについては、指定児童発達支援において、保育所その他の障害児が日常的に通う施設(以下この注において「保育所等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児に係る児童発達支援計画の作成または見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していないときは、算定しない。
注2 ロについては、指定児童発達支援事業所等において、保育所等施設との連携をはかるため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の保育所等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
注3 ハについては、指定児童発達支援事業所等において、児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
注4 ハについては、指定児童発達支援事業所等がして通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。
注5 ロについては、障害児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。
通所報酬告示第1の12の2の関係機関連携加算については、障害児が日々通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブその他の障害児が日常的に通う施設(以下この⑮の2において「保育所等施設」という。)又は
障害児の状況等によっては連携が必要となる児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この⑮の2において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、これらの施設又は関係機関と情報共有や連絡調整などを行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 関係機関連携加算(Ⅰ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で通所支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催すること。
会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。
- イ アの会議の開催に留まらず、保育所等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、通所支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、通所支援計画を作成又は見直しをすること。連携の具体的な方法等の記載に当たっては、関係機関との連絡調整等を踏まえていることが通所給付決定保護者にわかるよう留意すること。
- エ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時、その内容の要旨及び通所支援計画に反映させるべき内容を記録すること。
- 関係機関連携加算(Ⅱ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- イ アの会議の開催等に留まらず、保育所等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
- 関係機関連携加算(Ⅲ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童相談所等関係機関との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- イ アの会議の開催等に留まらず、児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
- オ 個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。
- 関係機関連携加算(Ⅳ)を算定する場合
- ア 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行する際にも切れ目なく支援を継続できるようにする観点から、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること。
- イ 就学時の加算とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の小学部に入学する際に連絡調整等を行った場合に算定できるものであること。
- ウ 就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連絡調整等を行った場合に算定できるものであるが、就職先が就労継続A型及びB型並びに就労移行支援事業所の場合は加算の対象とならないこと。
- エ 障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得たうえで就学先又は就職先に渡すこと。
なお、必ずしも会議の開催まで求めるものではないこと。
- オ 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手ややり取りの内容について記録をすること。
- その他
- ア 関係機関連携加算(Ⅰ)の場合においては、共生型児童発達支援事業所については、児童発達支援管理責任者を配置していないときには、算定できないこと。
- イ 関係機関連携加算(Ⅰ)と関係機関連携加算(Ⅱ)は、同一の月においていずれかのみ算定可能とする。
- ウ 保育所等訪問支援との多機能型事業所の場合、関係機関連携加算(Ⅲ)と保育所等訪問支援の関係機関連携加算は同一の月においていずれかのみ算定可能とする。
- エ 関係機関連携加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれの場合においても、障害児が複数の障害児通所支援事業所等で支援を受けている場合には、事業所間の連携についても留意するとともに、当該障害児が障害児相談支援事業を利用している場合には、連携に努めること。
なお、他の障害児通所支援事業所等との連携については加算の対象とはしないものであること。
放課後等デイサービス
| イ 関係機関連携加算(Ⅰ) | 250単位/回
(月1回を限度) |
| ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) | 200単位/回
(月1回を限度) |
| ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度) | 150単位/回
(月1回を限度) |
| ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度) | 200単位/回
(月1回を限度) |
注1 イについては、指定放課後等デイサービスにおいて、学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)、専修学校(同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程及び一般課程を除く。)をいう。)その他就学児が日常的に通う施設(以下この注において「学校等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児に係る放課後等デイサービス計画の作成または見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、1の注11のイ又はロを算定していないときは、算定しない。
注2 ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、学校等施設との連携をはかるため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該就学児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の学校等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
注3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、児童相談書、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
注4 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等がして通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、就学児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。
注5 ロについては、就学児が就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。
通所報酬告示第3の10の2の関係機関連携加算については、2の(1)の⑮の2を準用する。
2の(1)の⑮の2
通所報酬告示第1の12の2の関係機関連携加算については、障害児が日々通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブその他の障害児が日常的に通う施設(以下この⑮の2において「保育所等施設」という。)又は
障害児の状況等によっては連携が必要となる児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この⑮の2において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、これらの施設又は関係機関と情報共有や連絡調整などを行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 関係機関連携加算(Ⅰ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で通所支援計画の作成又は見直しに関する会議を開催すること。
会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、障害児が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。
- イ アの会議の開催に留まらず、保育所等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、通所支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、通所支援計画を作成又は見直しをすること。連携の具体的な方法等の記載に当たっては、関係機関との連絡調整等を踏まえていることが通所給付決定保護者にわかるよう留意すること。
- エ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時、その内容の要旨及び通所支援計画に反映させるべき内容を記録すること。
- 関係機関連携加算(Ⅱ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、障害児が日々通う保育所等施設との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- イ アの会議の開催等に留まらず、保育所等施設との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
- 関係機関連携加算(Ⅲ)を算定する場合
- ア あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童相談所等関係機関との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- イ アの会議の開催等に留まらず、児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
- ウ 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- エ アの会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。
- オ 個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。
- 関係機関連携加算(Ⅳ)を算定する場合
- ア 障害児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行する際にも切れ目なく支援を継続できるようにする観点から、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること。
- イ 就学時の加算とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の小学部に入学する際に連絡調整等を行った場合に算定できるものであること。
- ウ 就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連絡調整等を行った場合に算定できるものであるが、就職先が就労継続A型及びB型並びに就労移行支援事業所の場合は加算の対象とならないこと。
- エ 障害児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得たうえで就学先又は就職先に渡すこと。
なお、必ずしも会議の開催まで求めるものではないこと。
- オ 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合には、相手ややり取りの内容について記録をすること。
- その他
- ア 関係機関連携加算(Ⅰ)の場合においては、共生型児童発達支援事業所については、児童発達支援管理責任者を配置していないときには、算定できないこと。
- イ 関係機関連携加算(Ⅰ)と関係機関連携加算(Ⅱ)は、同一の月においていずれかのみ算定可能とする。
- ウ 保育所等訪問支援との多機能型事業所の場合、関係機関連携加算(Ⅲ)と保育所等訪問支援の関係機関連携加算は同一の月においていずれかのみ算定可能とする。
- エ 関係機関連携加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれの場合においても、障害児が複数の障害児通所支援事業所等で支援を受けている場合には、事業所間の連携についても留意するとともに、当該障害児が障害児相談支援事業を利用している場合には、連携に努めること。
なお、他の障害児通所支援事業所等との連携については加算の対象とはしないものであること。
保育所等訪問支援
注1 指定保育所等訪問支援において、訪問先の施設に加えて、児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況、生活環境その他の障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の訪問先の施設及び児童相談所等関係機関との連絡調整並びに必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
注2 指定保育所等訪問支援事業所が指定中初基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第1の12の2に規定する関係機関連携加算のハ、第3の10の2に規定する関係機関連携加算のハ、別表2経過的通所給付費単数表第1の16に規定する関係機関連携加算のハ、同表第2の16に規定する関係機関連携加算のハ又は同表第3の15に規定する関係機関連携加算のハを算定しているときは、算定しない。
通所報酬告示第5の1の8の関係機関連携加算については、訪問先の施設に加えて、障害児の状況等に応じて連携が必要となる児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この④の5において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、会議を開催等して児童相談所等関係機関と情報連携を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、児童相談所等関係機関との間で、障害児の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。
会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
- ❶の会議の開催等に留まらず、児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
- 会議又は連絡調整等を行った場合は、その出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
- ❶の会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、児童相談所等関係機関と連携した支援の提供を進めること。
その際、訪問先施設を含めた連携の取組となるよう努めること。
- 本加算及び通所報酬告示第1の12のハ又は同告示第3の10の2のハについて、児童発達支援又は放課後等デイサービスとの多機能型事業所の場合、合わせて月1回の算定を限度とする。
また、当該多機能型事業所の場合であって、加算対象児童が個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては、本加算を算定しない。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
関連記事
まとめ
「関係機関連携加算」は、障害福祉サービス事業における支援の質を向上させる重要な加算制度です。それぞれの区分で求められる要件を満たすことで、障害児とその家族がより安心して生活できる環境を整えます。事業者は、適切な記録管理と情報共有を徹底し、より良い支援体制を築くことが求められます。
あわせて読みたい
サービス横断メニュー