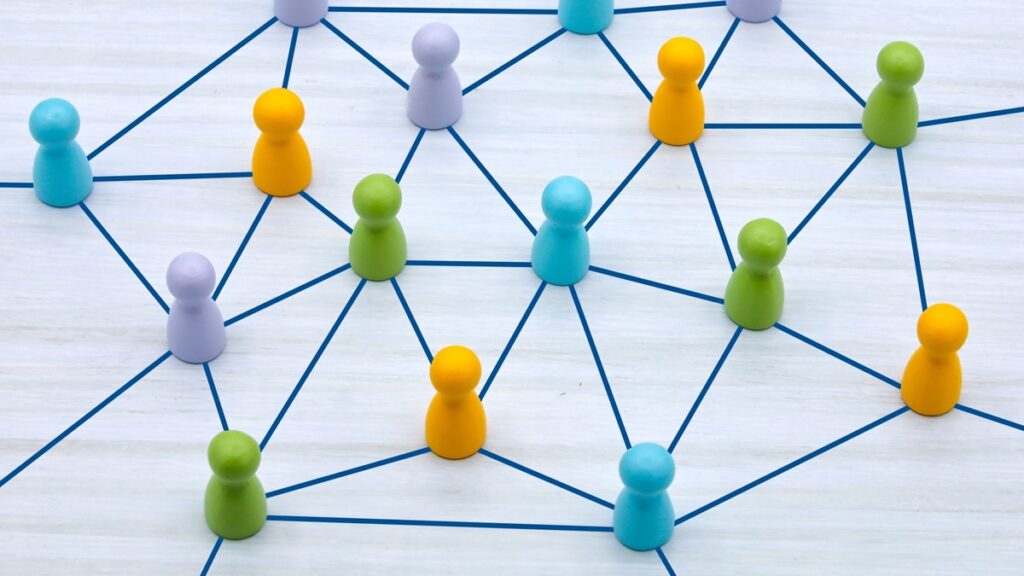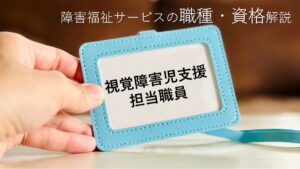障害福祉事業の「個別サポート加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次
「個別サポート加算」の概要
障害福祉サービスの現場では、対象者ごとに適切な支援を提供するために、さまざまな加算制度が用意されています。その中でも「個別サポート加算」は、重度の障害を持つ児童や、心理的・社会的支援が必要な児童へのケアを充実させるために設けられた重要な制度です。
個別サポート加算は、大きく分けて3つの種類(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(放デイ))があり、それぞれが異なる目的と条件を持っています。
この加算は、指定児童発達支援や放課後等デイサービスを提供する事業者が、特定の要件を満たす支援を行う際に、日々の支援内容に基づいて加算される仕組みです。
具体的には、重度の知的障害や肢体不自由を持つ児童への支援、要保護児童の心理的ケア、さらには不登校状態の児童に対する支援など、加算の適用範囲は多岐にわたります。本記事では、それぞれの加算の要件と注意点について、詳しく解説します。
対象サービス
算定要件など
児童発達支援の場合
加算(Ⅰ)
- 対象児童:
- 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児(重症心身障害児)
- 身体に重度の障害がある児童(1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児)
- 重度の知的障害がある児童(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児)
- 精神に重度の障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児)重度の知的障害・肢体不自由の重複障害児、身体・精神に重度の障害を持つ児童
加算(Ⅱ)
- 要保護児童・要支援児童を受け入れ、公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して指定児童発達支援を行う場合に算定
- 連携先機関等との情報共有は、6月に1回以上、記録を文書で保管
放課後等デイサービスの場合
1. 個別サポート加算(Ⅰ)
- 対象者:
- 市町村が認めた「著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児」。
- 就学児サポート調査表の評価で以下に該当。
- 合計13点以上(0~2点区分を各項目で算出)。
- 食事、排せつ、入浴、移動などの日常生活動作に全介助が必要な場合(3項目以上)。
- 加算条件:
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置。
- 研修修了者が対象児に指定放課後等デイサービスを行った場合、90単位に加え30単位を加算。
- 対象外:
- 重症心身障害児専用の事業所で支援を受ける重症心身障害児。
2. 個別サポート加算(Ⅱ)
- 対象者:
- 要件:
- 家庭や心理的に不安定な児童へのケアが必要。
- 公的機関や医師との連携が必須。
- 連携内容を6か月に1回以上文書で記録し保管。
- 障害児への支援状況を児童発達支援計画に記載し、保護者の同意を得る。
- 留意点:
- 関係機関連携加算(Ⅲ)は算定不可(本加算で評価済み)。
3. 個別サポート加算(Ⅲ)
- 対象者:
- 不登校状態の障害児。
- 「心理的・情緒的・身体的要因で登校が困難」と判断された児童(病気や経済的理由は除外)。
- 要件:
- 学校や家族と緊密に連携して支援を実施。
- 学校との情報共有を月1回以上行い、記録を作成・共有。
- 家族への相談援助を月1回以上実施。
- 障害児の登校状況や支援の継続要否を学校と事業所で検討。
- 注意事項:
- 関係機関連携加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、家族支援加算(Ⅰ)は算定不可。
その他共通事項
- 必要な支援内容や連携状況について、市町村からの確認に回答する義務がある。
- 記録は文書化し、適切に保管すること。口頭のメモのみは不可。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
児童発達支援
| イ 個別サポート加算(Ⅰ) | 120単位/日 |
| ロ 個別サポート加算(Ⅱ) | 150単位/日 |
注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、重症心身障害児、身体に重度の障害がある児童、重度の知的障害がある児童又は精神に重度の障害がある児童に対し、指定児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のハを算定しているときは、加算しない。
注2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て、児童相談所、こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
⑫の6 個別サポート加算(Ⅰ)の取扱い
通所報酬告示第1の9のイの個別サポート加算(Ⅰ)については、著しく重度の障害児への支援を充実させる観点から、当該障害児に対して指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、対象となる児童を以下のとおりとする。
なお、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合として基本報酬を算定している場合については、本加算を算定しない。
- 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児(重症心身障害児)
- 身体に重度の障害がある児童(1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児)
- 重度の知的障害がある児童(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児)
- 精神に重度の障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児)
⑫の7 個別サポート加算(Ⅱ)の取扱い
通所報酬告示第1の9のロの個別サポート加算(Ⅱ)については、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して指定児童発達支援を行う場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算の趣旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること。
- 児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師(以下「連携先機関等」という。)と、障害児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
- 連携先機関等との❶の共有は、6月に1回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。
なお、ここでいう文書は、連携先機関等が作成した文書又は児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象とならない。
- ❶のように、連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置付け、通所給付決定保護者の同意を得ること。
- 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
- 当該加算を算定するために必要な児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携については、当該加算で評価しているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しない。
その他の観点により、医療機関との連携を行った場合には、この限りではない。
放課後等デイサービス
| イ 加算(Ⅰ) | イ ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合 | 90単位/日 |
| ロ 著しく重度の障害児に支援を行った場合 | 120単位/日 |
| ロ加算(Ⅱ) | 150単位/日 |
| ハ加算(Ⅲ) | 70単位/日 |
注1 イの(1)については、指定放課後等デイサービス事業所等において、 行動上の課題を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、 1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イの(2)又は1の口を算定しているときは、加算しない。
注1の2 イの(1)を算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイ サービス事業所であって、 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、 行動上の課題を有する就学児に対して、 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
注1の3 イの(2)については、著しく重度の障害を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス 事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、 イの(1)又は1の口を算定しているときは、加算しない。
注2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所、こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
注3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、不登校の就学児に対して、学校及び家族等と連携して指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
⑫の5 個別サポート加算(Ⅰ)の取扱い
通所報酬告示第3の7のイの個別サポート加算(Ⅰ)については、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させる観点から、就学児サポート調査表(270号告示の8の4の表並びに食事、排せつ、入浴及び移動の項目をいう。)のうち、以下の❶又は❷に該当すると市町村が認めた障害児について評価を行うものであること。
- 通所報酬告示第3の7のイの(1)を算定する場合就学児サポート調査表(外部リンク)の各項目について、その項目が見られる頻度等をそれぞれ0点の欄から2点の欄までの区分に当てはめて算出した点数の合計が13点以上であること。
なお、通所報酬告示第3の7のイの(1)を算定する場合において、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)し、当該研修修了者が本加算の対象児に指定放課後等デイサービスを行った場合、90単位に加え1日につき30単位を所定単位数に加算すること。
- 通所報酬告示第3の7のイの(2)を算定する場合食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とすること。
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を受ける重症心身障害児については加算しない。
⑫の6 個別サポート加算(Ⅱ)の取扱い
通所報酬告示第3の7のロの個別サポート加算(Ⅱ)については、2の(1)の⑫の7を準用する。
2の(1)の⑫の7
通所報酬告示第1の9のロの個別サポート加算(Ⅱ)については、要保護児童又は要支援児童を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して指定児童発達支援を行う場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
ただし、これらの支援の必要性について、通所給付決定保護者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算の趣旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること。
- 児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師(以下「連携先機関等」という。)と、障害児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
- 連携先機関等との❶の共有は、6月に1回以上行うこととし、その記録を文書で保管すること。
なお、ここでいう文書は、連携先機関等が作成した文書又は児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものであり、単に児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象とならない。
- ❶のように、連携先機関等と障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置付け、通所給付決定保護者の同意を得ること。
- 市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
- 当該加算を算定するために必要な児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師との連携については、当該加算で評価しているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定しない。
その他の観点により、医療機関との連携を行った場合には、この限りではない。
⑫の7 個別サポート加算(Ⅲ)の取扱い
通所報酬告示第3の7のハの個別サポート加算(Ⅲ)については、不登校の状態にある障害児に対して、学校及び家族等と緊密に連携を図りながら、指定放課後等デイサービスを行う場合に評価を行うものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 本加算の対象となる不登校の状態にある障害児とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」であって、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童とする。
- 学校と日常的な連携を図り、障害児に対する支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。通所支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成を行うこと。
- 学校との情報共有を、月に1回以上行うこと。その実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成し、学校に共有すること。情報共有は対面又はオンラインにより行うこと。
- 家族への相談援助を月に1回以上行うこと。
相談援助は、居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも問わないが、個別での相談援助を行うこと。
また、相談援助を行う場合には、障害児や家族の意向及び居宅での過ごし方の把握、放課後等デイサービスにおける支援の実施状況等の共有を行い、実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成すること。
- ❸の学校との情報共有においては、障害児の不登校の状態について確認を行うこととし、障害児や家族等の状態や登校状況等を考慮した上で、学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと。
その結果、本加算の算定を終結する場合にあっても、その後の支援においては、学校との連携に努めること。
- 市町村(教育関係部局、障害児関係部局)から、家庭や学校との連携状況や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答するものとする。
- ❸の学校との連携及び❹の家族等への相談援助については、関係機関連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)、家族支援加算(Ⅰ)は算定できない。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
関連記事
まとめ
「個別サポート加算」は、障害福祉サービスにおいて、特に手厚い支援が求められる児童に対応するための重要な仕組みです。本記事では、加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のそれぞれについて、その目的や要件を具体的に解説しました。
この加算を活用することで、事業者は対象児童により適切で質の高い支援を提供することが可能になります。しかし、制度を適用するには、各加算の要件を正確に理解し、必要な連携や文書作成を怠らないことが求められます。
あわせて読みたい
サービス横断メニュー