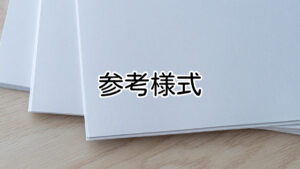障害福祉事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?適用条件と注意点!
2024
11/25
目次
「医療・保育・教育機関等連携加算」の概要
「医療・保育・教育機関等連携加算」とは、障害福祉事業者が他の機関と連携して利用者への支援を強化するために設けられた制度です。この加算は、利用者が利用する医療機関、保育所、学校などと情報を共有し、支援計画に反映させることを評価するものです。
例えば、病院の職員と面談し情報を得る、通院同行の際に医療機関と情報を共有する、または他機関から求めに応じて情報提供を行う場合が対象です。このような取り組みにより、利用者の生活環境や支援方法に関する情報が一貫性を持ち、支援の質を向上させることができます。
対象サービス
適用条件など
■ 算定条件
利用者情報の共有を目的とした面談や会議。
通院同行での情報提供。
他機関からの求めに応じた情報提供。
■ 算定の注意点
面談はオンライン会議形式も可能。
初回加算や退院加算と重複する場合は算定不可。
同一機関での通院同行と情報提供の重複は不可。
■ 単位数と限度回数
面談や情報提供で200~300単位。
各算定対象ごとに月1回まで。
※詳細は報酬告示と留意事項 を参照ください。
\遠隔地の場合、こちらの加算も算定できる可能性あり!/
あわせて読みたい
障害福祉事業の「遠隔地訪問加算」とは?適用条件と注意点を解説!
遠隔地訪問加算 特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、一部の加算を算…
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度
面談(計画作成月) 200単位/月 面談(モニタリング月 )300単位/月 通院同行 300単位/回 情報提供 150単位/回
注1 指定特定相談支援事業者 が、次の❶ から❸ までに該当する場合に、1月にそれぞれ❶ から❸ までに掲げる単位数を加算する。
指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する機関(以下「福祉サービス等提供機関」という。 )(障害福祉サービス等を行う者を除く。 ❸ 、注2及び10の注において同じ。 )の職員等と面談又は会議を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合(計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とし、3の 初回加算 を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けているときを除く。 ) 次の❶ 又は➋ に掲げる場合に応じ、それぞれ❶ 又は➋ に掲げる単位数
指定サービス利用支援を行った場合 200単位
指定継続サービス利用支援を行った場合 300単位
計画相談支援対象障害者等が病院等に通院するに当たり、当該病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。 )(1のイ又はロを算定する場合に限る。 )300単位
福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報を提供合に限る。)
注2 注1の❸ については、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
⑴ 病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)
⑵ 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
趣旨
福祉サービス等提供機関の職員との面談等 利用者への通院同行 福祉サービス等提供機関への情報提供
算定に当たっての留意事項
連携の対象機関 福祉サービス等提供機関の職員との面談等 初回加算 を算定する場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は算定することができないものであること。 利用者への通院同行 福祉サービス等提供機関への情報提供 加算の算定方法
手続
障害児相談支援
※面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度
面談(計画作成月):1月につき200単位を加算 面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算 通院同行:1回につき300単位を加算 情報提供:1回につき150単位を加算
注1 指定障害児相談支援事業者が次の❶ から❸ までに該当する場合に、1月にそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数を加算する。
指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する基幹(以下「福祉サービス等提供期間」という。)(障害児通所支援及び障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を行うものを除く、❸ 、注2及び10の注において同じ。)の職員等と面談又は会議を行い、障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った場合(障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人に月1月に1回を限度とし、3の初回加算を算定する場合及び6の退院・退所加算を算定する場合であって、退院、退所等をする施設の職員のみから情報の提供を受けている場合を除く。)次の①又は②に掲げる場合に応じ、それぞれ①又は②に掲げる単位数
指定障害児支援利用援助を行った場合:200単位
指定継続障害児支援利用援助を行った場合:300単位
障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合(1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とする。1のイ又はロを算定する場合に限る。):300単位
福祉サービス等提供期間からの求めに応じて、福祉サービス等提供期間に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合(1のイ又はロを算定する場合に限る。):150単位
注2 注1の❸ については、次の❶ 又は❷ に掲げる福祉サービス等提供期間ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度とする。
病院等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等(以下「訪問看護ステーション等」という。)
福祉サービス等提供期間(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
(1) 趣旨
当該加算は、障害児が利用する病院等、訪問看護事業所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等の関係機関との日常的な連携体制を構築するとともに、障害児の状態や支援方法の共有を行うことを目的とするものであるから、当該加算の算定場面に限らず、関係機関との日常的な連絡調整に努めること。
① 福祉サービス等提供機関の職員との面談等 ② 障害児への通院同行 ③ 福祉サービス等提供機関への情報提供
(2) 算定に当たっての留意事項
① 連携の対象機関 ② 福祉サービス等提供機関の職員との面談等 ③ 利用者への通院同行 ④ 福祉サービス等提供機関への情報提供
㈠ 病院等、訪問看護事業所
㈡ ㈠以外の福祉サービス等提供機関
⑤ 加算の算定方法
(3) 手続
第四の8の(3)の規定を準用する。
第四の8の(3)
退院、退所する施設の職員と面談を行い情報の提供を受けた場合には、相手や面談日時、その内容の要旨及び障害児支援利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
あわせて読みたい
【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の福祉サービス等提供機関の対象とは?│R6,03,29問67~68
(福祉サービス等提供機関の対象)問 67 医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても…
厚生労働省の関連情報・様式など
関連するQ&A
関連記事
まとめ
障害福祉事業における「医療・保育・教育機関等連携加算」は、利用者の支援を強化するために他機関との連携を促進する制度です。適切な情報共有と連携体制の構築により、利用者の生活や医療、教育の質を向上させることができます。加算の適用には、対象機関や算定条件を正確に理解し、必要な要件を満たすことが求められます。この加算を活用することで、事業者は利用者にとって最適な支援を提供できるでしょう。
あわせて読みたい
サービス横断メニュー