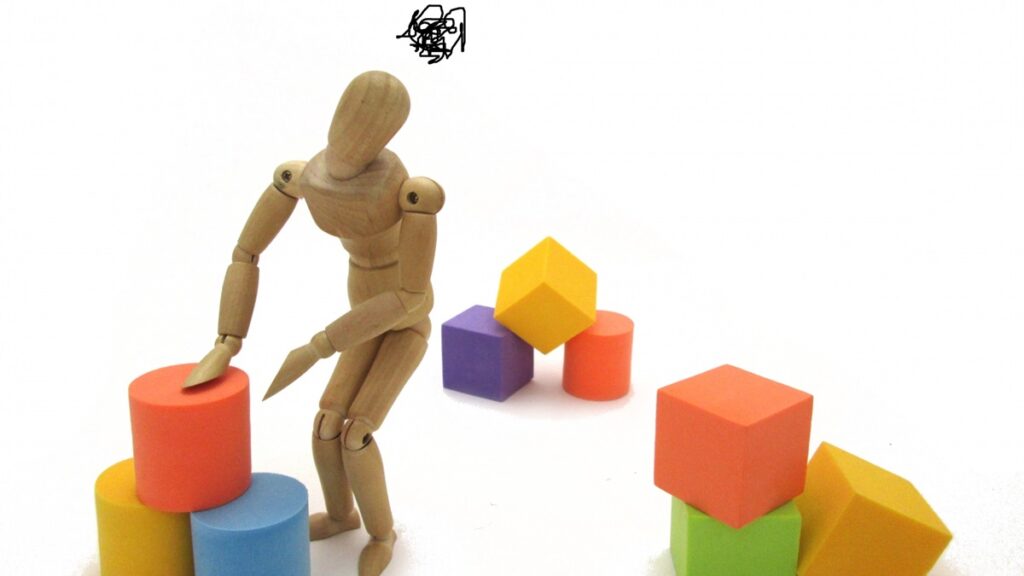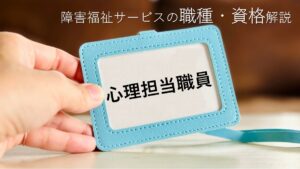「ソーシャルワーカー配置加算」の概要
「ソーシャルワーカー配置加算とは?」
ソーシャルワーカー配置加算は、障害福祉サービスにおいて、障害児が施設を退所して地域生活に移行する際の支援を充実させるために設けられた仕組みです。障害児入所施設で一定条件を満たす場合、1日あたりの所定単位数に加算されます。
背景には、障害児が地域で自立した生活を送ることを支援する重要性が高まっていることがあります。施設内での生活だけでなく、退所後の生活にスムーズに適応するためには、地域や家族と連携した支援が欠かせません。この役割を果たすのが、ソーシャルワーカーです。
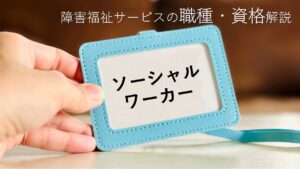
対象サービス
算定要件など
- ソーシャルワーカーの資格要件は社会福祉士または5年以上の実務経験。
- 退所後の支援計画の立案と地域連携が主な業務内容。
- 継続的な相談支援や入退所の調整も含まれる。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士又は5年以上障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に従事した者(以下「社会福祉士等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 知的障害児の場合
| (1)定員10人以下 | 159単位 |
| (2)定員11~20人 | 79単位 |
| (3)定員21~30人 | 53単位 |
| (4)定員31~40人 | 40単位 |
| (5)定員41~50人 | 32単位 |
| (6)定員51~60人 | 26単位 |
| (7)定員61~70人 | 23単位 |
| (8)定員71~80人 | 20単位 |
| (9)定員81~90人 | 18単位 |
| (10)定員91~100人 | 16単位 |
| (11)定員101人~ | 14単位 |
ロ 自閉症児の場合
| (1)定員30人以下 | 53単位 |
| (2)定員31~40人 | 40単位 |
| (3)定員41~50人 | 32単位 |
| (4)定員51~60人 | 26単位 |
| (5)定員61~70人 | 23単位 |
| (6)定員71人~ | 20単位 |
ハ 盲児又はろうあ児の場合
| (1)定員5~10人 | 159単位 |
| (2)定員11~15人 | 106単位 |
| (3)定員16~20人 | 79単位 |
| (4)定員21~25人 | 63単位 |
| (5)定員26~30人 | 53単位 |
| (6)定員31~35人 | 45単位 |
| (7)定員36~40人 | 40単位 |
| (8)定員41~50人 | 32単位 |
| (9)定員51~60人 | 26単位 |
| (10)定員61~70人 | 23単位 |
| (11)定員71~80人 | 20単位 |
| (12)定員81~90人 | 18単位 |
| (13)定員91人~ | 16単位 |
ニ 肢体不自由児の場合
| (1)定員50人以下 | 32単位 |
| (2)定員51~60人 | 26単位 |
| (3)定員61~70人 | 23単位 |
| (4)定員71人~ | 20単位 |
留意事項
入所報酬告示第1の1の注14のソーシャルワーカー配置加算は、指定福祉型障害児入所施設において、地域における生活に移行するに当たり、共同生活援助サービスの利用及び障害者支援施設への入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携し、以下の❶から❻に掲げる業務を専ら行うソーシャルワーカー(①社会福祉士、②障害福祉サービス事業、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援に5年以上従事した経験を有する者)を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。
なお、これらの移行に向けた取組については、入所後早期の段階から移行を見据え、入所児童の意向、特性等に関する必要なアセスメント等を行い把握したうえで、適切な時期から計画的に行うこと。
また、既にこれらの取組を行っている福祉型障害児入所施設においては、入所児童や保護者との信頼関係の構築の観点から、これまで、施設内でこれらの取組を担当してきた職員が、入所児童や保護者への説明等に係る業務をソーシャルワーカーと協力して行うことも差し支えないものとする。
- 移行に関する入所児童(18歳以上の者を含む。以下⑧の4において同じ。)及び保護者に対する相談援助を行う。
- 移行に当たり児童相談所をはじめ多機関・多職種が協働できるように支援の調整を図る。
- 移行に当たり障害者総合支援法第89条の3に規定する協議会等の場を活用し、必要な社会資源の開発・改善を行う役割を担う。
- 入所児童が退所後の生活がイメージできるような体験の機会や、移行先の生活に適応できるよう訓練等の機会を提供する。
- 支援の継続性を図る観点より、退所後においても、必要に応じて児童相談所及び相談支援事業所等からの要請に応じて継続的な相談援助を行う。
- 児童発達支援管理責任者と連携し、児童の入退所や外泊に係る調整を行う。
Q&A
関連記事
\事業者必須!/
まとめ
「ソーシャルワーカー配置加算」は、障害児の地域生活への移行を支援するための重要な制度です。この加算を活用することで、施設と地域、家族の連携を強化し、障害児の自立した生活をサポートする体制を整えることができます。施設運営者や支援者にとっては、条件をしっかり理解し、効果的に制度を活用することが鍵となります。