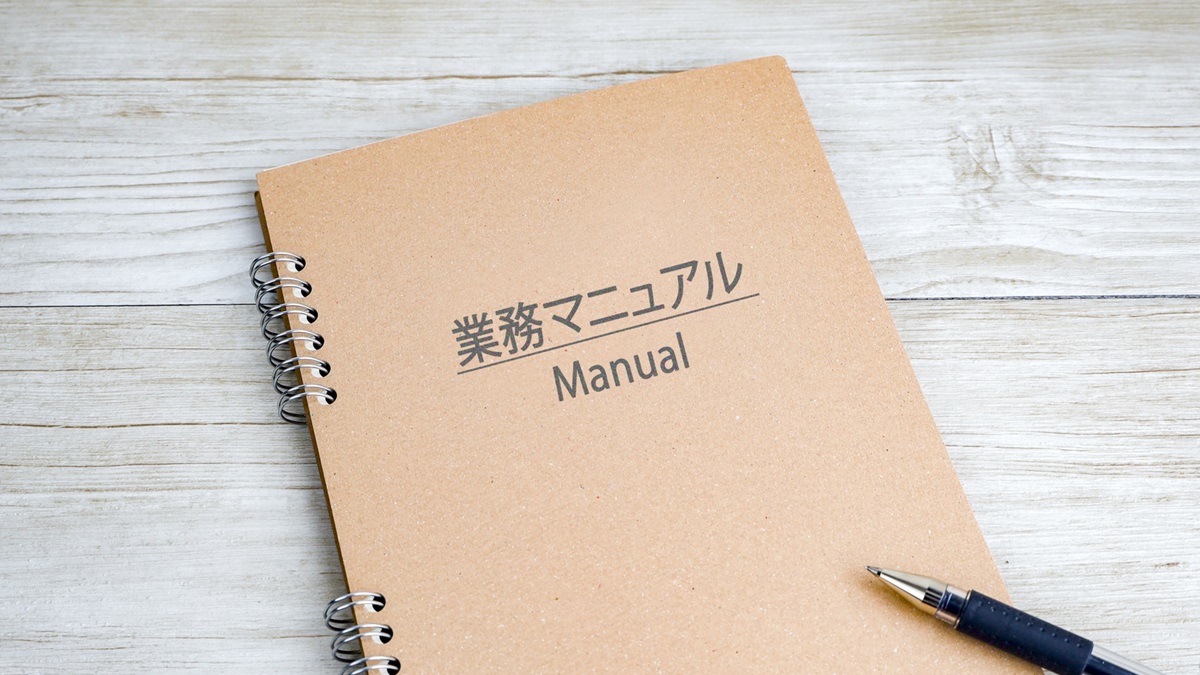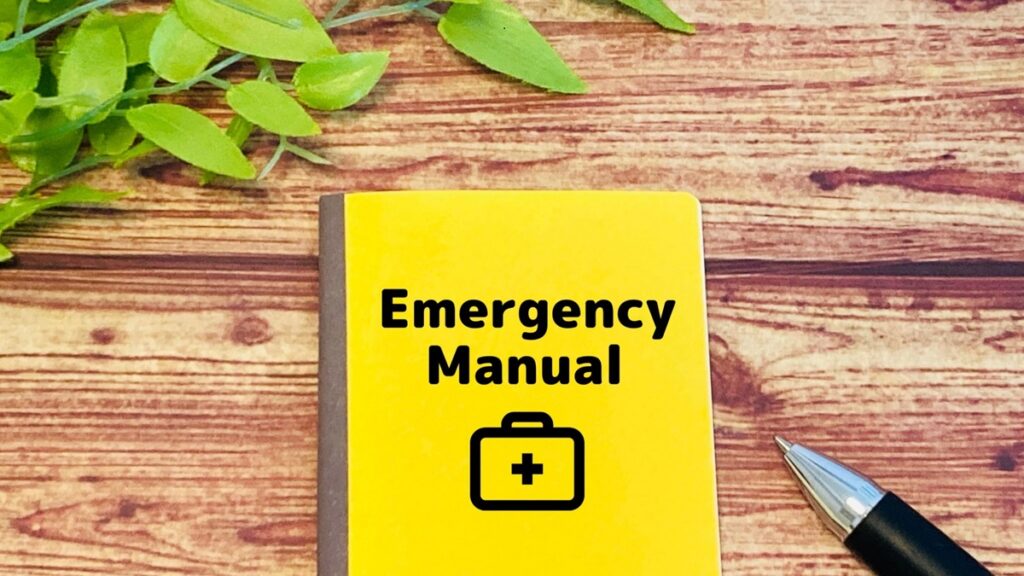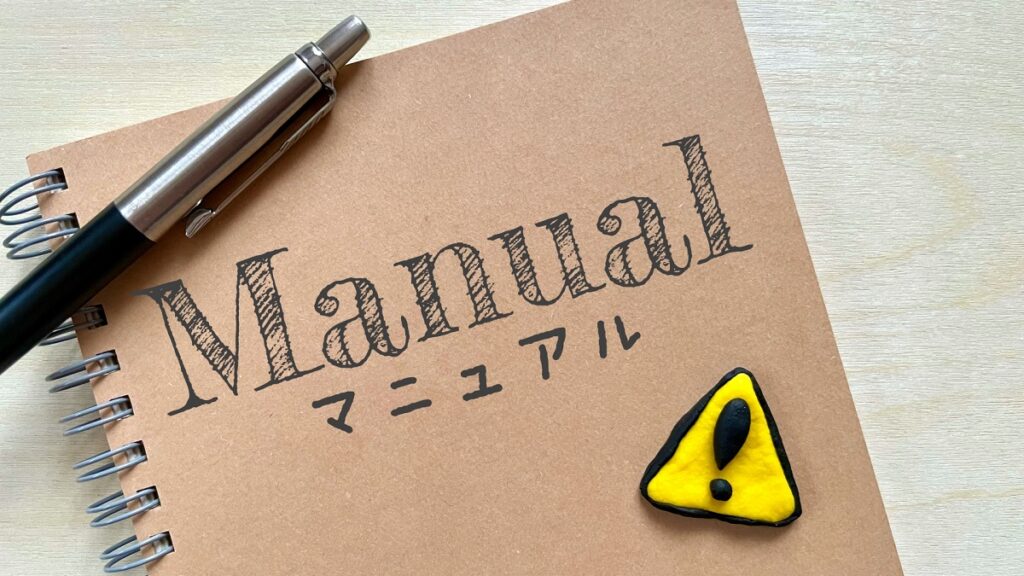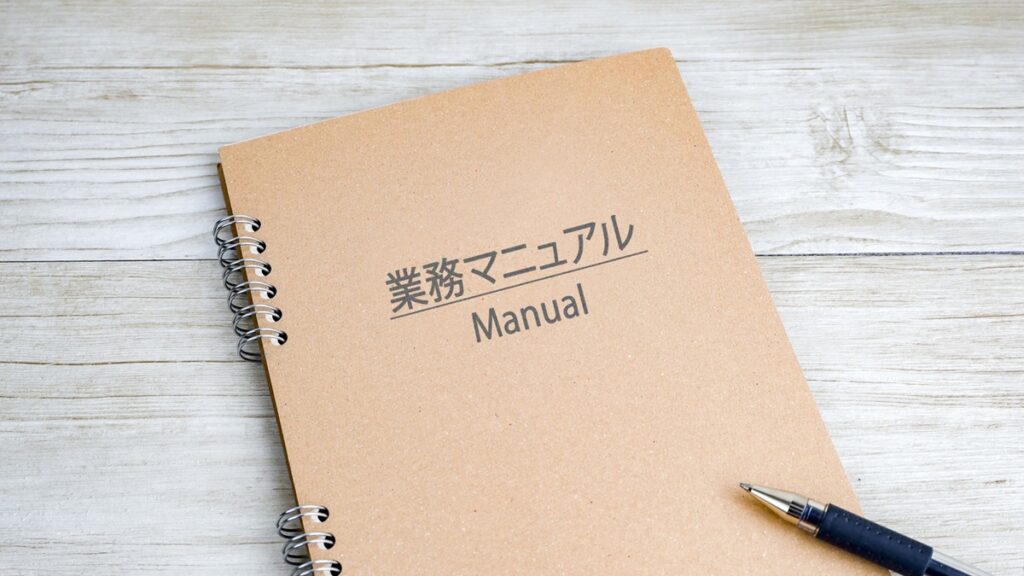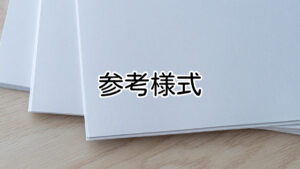衛生管理・感染症対策について
はじめに
障害福祉事業所では、利用者と従業員の健康を守るために、衛生管理と感染症対策が不可欠です。特に、新型コロナウイルスの流行以降、これらの重要性はさらに増しています。
厚生労働省の指定基準第34条では、事業所に対し、従業員の清潔保持と健康管理、設備の衛生的な管理を求めています。
また、感染症の発生やまん延を防ぐための具体的な取り組みとして、感染症対策委員会の設置や予防指針の整備、定期的な研修の実施が挙げられます。これらを実施することで、事業所の信頼性を高め、安全で安心な環境を提供することが可能になります。
指定基準と解釈通知
指定基準:衛生管理等(第34条)
- 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
- 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
- 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

解釈通知:(24)衛生管理等(基準第34条)
- 基準第34条第1項及び第2項は、指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定居宅介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。
特に、指定居宅介護事業者は、従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 - 同条第3項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的には次のアからウまでの取扱いとすること。
各事項について、同項に基づき指定居宅介護事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
- ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。
構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。
感染対策委員会は、利用者の状況など指定居宅介護事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。感染対策委員会は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。
ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。
この際、厚生労働省「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。
また、指定居宅介護事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 - イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
当該指定居宅介護事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。
平常時の対策としては、指定居宅介護事業所内の衛生管理(環境の整備等)、支援にかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。
また、発生時における指定居宅介護事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。 - ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。
職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定居宅介護事業所が定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
なお、研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(外部リンク)等を活用するなど、指定居宅介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定居宅介護事業所の実態に応じ行うこと。
また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)に行うことが必要である。
訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
- ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

感染症対策の基本構成
障害福祉事業所で感染症対策を徹底するには、具体的なマニュアルの整備が重要です。このマニュアルは、事業所内での対策を統一し、迅速な対応を可能にする指針となります。
まず、感染症予防の対策を話し合う場として感染症対策委員会を設置します。この委員会は、看護師や福祉職員など多職種が連携して構成するのが理想的です。必要に応じて、外部の感染症専門家のアドバイスを受けると、より効果的な対策が実現します。委員会は年2回以上の定期開催が推奨され、感染症流行時には緊急で招集できる体制を整えておく必要があります。
次に、感染症予防と対応の指針を作成します。この指針には、平常時の衛生管理(手洗い・設備清掃)や発生時の対応(状況把握、感染拡大の防止、関係機関との連携)が含まれます。また、緊急時の連絡体制を明確にし、全職員に共有することが重要です。具体的な記載例は、厚生労働省の感染対策マニュアルを参考にすると良いでしょう。
参考:「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」
従業員の教育と訓練
感染症対策を徹底するためには、従業員への教育と訓練が欠かせません。適切な知識を職員全員が持つことで、現場での迅速な対応が可能になります。
訓練の実施
感染症発生を想定したシミュレーション訓練を実施します。訓練では、緊急時の連絡フローや役割分担の確認、感染対策を施した支援演習を行います。机上訓練と実地訓練を組み合わせ、実践的なスキルを身につけましょう。
研修の実施
年1回以上、感染症予防の研修を行い、手洗いや防護具の使用方法、事業所独自の指針の理解を深めます。新規採用時にも感染症対策研修を実施することで、新しい職員がスムーズに現場に適応できます。
参考様式
\事業者必須!/
まとめ
障害福祉事業所における衛生管理と感染症対策は、利用者と職員の安全を守るための重要な取り組みです。感染症対策委員会の設置や指針の整備、従業員教育と訓練の実施を通じて、事業所全体で感染リスクを軽減する環境を整えましょう。
具体的なマニュアルの作成や実践事例を参考にすることで、事業所の信頼性を高め、安心・安全な支援を提供できます。衛生管理を徹底し、感染症に強い事業所を目指しましょう!