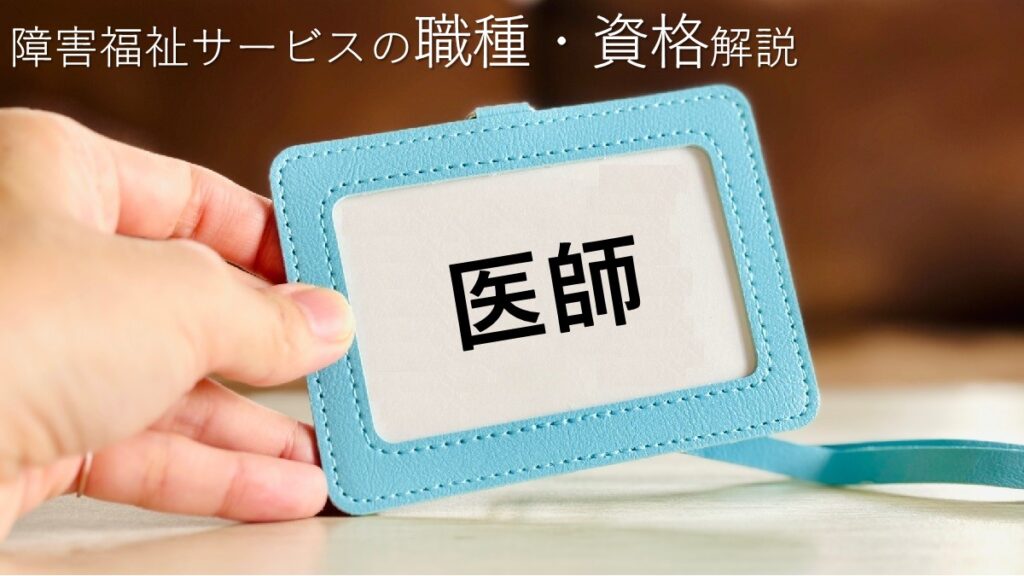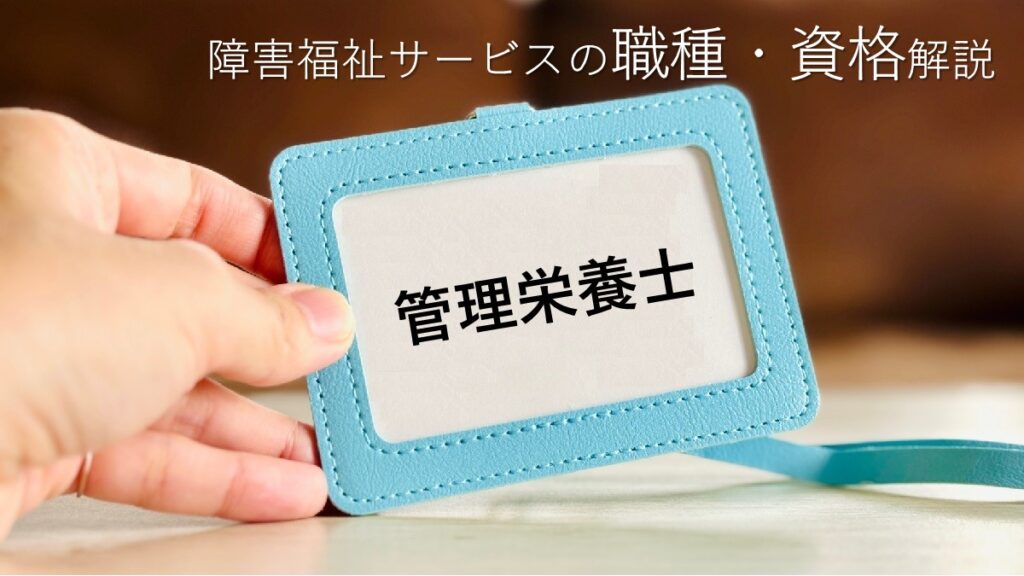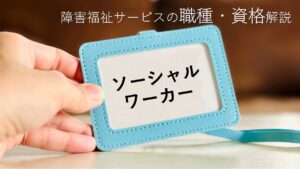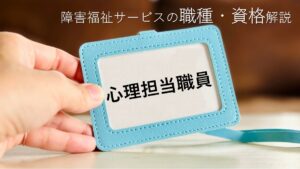【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第123号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF
第1 福祉型障害児入所施設
1 福祉型障害児入所施設給付費(1日につき)
イ 知的障害児の場合
| (1)定員5人以上9人以下 | 当該施設が単独施設 | 957単位 |
| (2)定員10人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 837単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,727単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 957単位 | |
| (3)定員11人以上15人以下 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 665単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,109単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 878単位 | |
| (4)定員16人以上20人以下 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 645単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,075単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 852単位 | |
| (5)定員21人以上25人以下 | 837単位 | |
| (6)定員26人以上30 人以下 | 812単位 | |
| (7)定員31人以上35人以下 | 700単位 | |
| (8)定員36人以上40 人以下 | 665単位 | |
| (9)定員41人以上50人以下 | 625単位 | |
| (10)定員51人以上60人以下 | 600単位 | |
| (11)定員61人以上70人以下 | 578単位 | |
| (12)定員71人以上80人以下 | 554単位 | |
| (13)定員81人以上90人以下 | 535単位 | |
| (14)定員91人以上100人以下 | 513単位 | |
| (15)定員101人以上 | 493単位 | |
ロ 自閉症児の場合
| (1)定員30人以下 | 845単位 |
| (2)定員31人以上40人以下 | 772単位 |
| (3)定員41人以上50人以下 | 734単位 |
| (4)定員51人以上60人以下 | 701単位 |
| (5)定員61人以上70人以下 | 668単位 |
| (6)定員71人以上 | 637単位 |
ハ 盲児の場合
| (1)定員5人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 1,246単位 |
| (ニ)当該施設が単独施設 | 988単位 | |
| (2)定員6~9人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 907単位 |
| (ニ)当該施設が単独施設 | 988単位 | |
| (3)定員10人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 907単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,903単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 988単位 | |
| (4)定員11~15人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 694単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,360単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 900単位 | |
| (5)定員16~20人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 644単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,142単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 900単位 | |
| (6)定員21~25人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 577単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,022単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 871単位 | |
| (7)定員26~30人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 542単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 871単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 871単位 | |
| (8)定員31~35人 | (一)当該施設が主たる施設 | 767単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 767単位 | |
| (9)定員36~40人 | (一)当該施設が主たる施設 | 713単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 713単位 | |
| (10)定員41~50人 | (一)当該施設が主たる施設 | 626単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 626単位 | |
| (11)定員51~60人 | (一)当該施設が主たる施設 | 603単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 603単位 | |
| (12)定員61~70人 | (一)当該施設が主たる施設 | 582単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 582単位 | |
| (13)定員71~80人 | (一)当該施設が主たる施設 | 560単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 560単位 | |
| (14)定員81~90人 | (一)当該施設が主たる施設 | 540単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 540単位 | |
| (15)定員91人~ | (一)当該施設が主たる施設 | 519単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 519単位 |
二 ろうあ児の場合
| (1)定員5人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 1,246単位 |
| (ニ)当該施設が単独施設 | 983単位 | |
| (2)定員6~9人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 929単位 |
| (ニ)当該施設が単独施設 | 983単位 | |
| (3)定員10人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 929単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,889単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 983単位 | |
| (4)定員11~15人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 695単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,349単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 895単位 | |
| (5)定員16~20人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 647単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 1,139単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 895単位 | |
| (6)定員21~25人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 573単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 966単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 866単位 | |
| (7)定員26~30人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 545単位 |
| (ニ)当該施設が主たる施設 | 866単位 | |
| (三)当該施設が単独施設 | 866単位 | |
| (8)定員31~35人 | (一)当該施設が主たる施設 | 763単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 763単位 | |
| (9)定員36~40人 | (一)当該施設が主たる施設 | 710単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 710単位 | |
| (10)定員41~50人 | (一)当該施設が主たる施設 | 623単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 623単位 | |
| (11)定員51~60人 | (一)当該施設が主たる施設 | 600単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 600単位 | |
| (12)定員61~70人 | (一)当該施設が主たる施設 | 580単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 580単位 | |
| (13)定員71~80人 | (一)当該施設が主たる施設 | 558単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 558単位 | |
| (14)定員81~90人 | (一)当該施設が主たる施設 | 537単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 537単位 | |
| (15)定員91人~ | (一)当該施設が主たる施設 | 518単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 518単位 |
ホ 肢体不自由児の場合
| (1)定員50人以下 | 766単位 |
| (2)定員51~60人 | 752単位 |
| (3)定員61~70人 | 737単位 |
| (4)定員71人~ | 720単位 |
注1 地方公共団体が設置する場合
指定福祉型障害児入所施設(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「指定入所基準」という。)第2条第1号に規定する指定福祉型障害児入所施設をいう。以下同じ。)において、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別及び入所定員に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
ただし、地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。
注2 利用定員超過・個別支援計画未作成 減算
注2 イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合
別にこども家庭庁長官が定める割合※利用定員超過減算 - 指定入所支援の提供に当たって、指定入所基準第21条の規定に従い、入所支援計画(同条第1項に規定する入所支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合(個別支援計画未作成減算)
- 入所支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- 入所支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50


注3 身体拘束廃止未実施減算
| 所定単位数の10/100単位 減算 |
指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。


注3の2 虐待防止措置未実施減算
| 所定単位数の1/100単位 減算 |
指定入所基準第42条第2項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。


注3の3 業務継続計画未策定減算
| 所定単位数の3/100単位 減算 |
指定入所基準第35条の2第1項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。



注3の4 情報公表未報告減算
| 所定単位数の5/100単位 減算 |
法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 日中活動支援加算
別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、日中活動支援加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合
| (1)定員が5~9人 | 当該施設が単独施設 | 67単位 |
| (2)定員10人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 161単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 67単位 | |
| (3)定員11~15人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 121単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 67単位 | |
| (3)定員11~15人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 121単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 67単位 | |
| (4)定員16~20人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 81単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 67単位 | |
| (5)定員21~25人 | 67単位 | |
| (6)定員26~30人 | 54単位 | |
| (7)定員31~35人 | 47単位 | |
| (8)定員36~40人 | 40単位 | |
| (9)定員41~50人 | 32単位 | |
| (10)定員51~60人 | 27単位 | |
| (11)定員61~70人 | 23単位 | |
| (12)定員71~80人 | 20単位 | |
| (13)定員81~90人 | 18単位 | |
| (14)定員91~100人 | 16単位 | |
| (15)定員101人~ | 16単位 |
ロ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合
| (1)定員30人以下 | 54単位 |
| (2)定員31~40人 | 40単位 |
| (3)定員41~50人 | 32単位 |
| (4)定員51~60人 | 27単位 |
| (5)定員61~70人 | 23単位 |
| (6)定員71人~ | 23単位 |
ハ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合
| (1)定員5人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 322単位 |
| (ニ)当該施設が単独施設 | 54単位 | |
| (2)定員6~9人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 | 179単位 |
| (ニ)当該施設が単独施設 | 54単位 | |
| (3)定員10人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 又は当該施設が主たる施設 | 161単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 54単位 | |
| (4)定員11~15人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 又は当該施設が主たる施設 | 107単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 54単位 | |
| (5)定員16~20人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 又は当該施設が主たる施設 | 81単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 54単位 | |
| (6)定員21~25人 | (一)当該施設に併設する施設が主たる施設 又は当該施設が主たる施設 | 64単位 |
| (二)当該施設が単独施設 | 54単位 | |
| (7)定員26~30人 | 54単位 | |
| (8)定員31~35人 | 46単位 | |
| (9)定員36~40人 | 40単位 | |
| (10)定員41~50人 | 32単位 | |
| (11)定員51~60人 | 27単位 | |
| (12)定員61~70人 | 23単位 | |
| (13)定員71~80人 | 20単位 | |
| (14)定員81~90人 | 18単位 | |
| (15)定員91人~ | 18単位 |

注5 重度障害児支援加算
| イ | 165単位 |
| ロ | 198単位 |
| ハ | 158単位 |
| 二 | 189単位 |
| ホ | 143単位 |
| へ | 171単位 |
| ト | 198単位 |
別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、重度障害児(次のイに規定する障害児、次のハ及びホに規定する盲児又はろうあ児並びに次のトに規定する肢体不自由児をいう。以下この第1において同じ。)に対し、指定入所支援を行った場合(イ、ロ又はトについては、該当する重度障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、重度障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
- イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
- (1)次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
- (一)食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
- (二)頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
- (一)食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
- (2)盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
- (1)次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
- ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
- (1) 6歳未満である者
- (2) 医療型障害児入所施設(法第42条第2号の医療型障害児入所施設をいう。)(主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる施設に限る。)を退所後3年未満である者
- (3) 入所後1年未満である者
- (1) 6歳未満である者
- ハ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ニに該当する場合を除く。) 158単位
- (1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
- (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄及び衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
- ニ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ハに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 189単位
- ホ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ヘに該当する場合を除く。) 143単位
- (1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
- (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
- (1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
- ヘ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ホに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 171単位
- ト 主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
- (1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
- (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又は喀痰吸引等を必要とする者

注5の2 重度障害児支援加算(別の要件に合致する場合)
注5の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注5のイの(1)の(二)又はハの(1)若しくはホの(1)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

注6 重度重複障害児加算
| 111単位/日 |
注5のイからト(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。
ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

注7 強度行動障害児特別支援加算
| イ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ) ※加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間+700単位 | 390単位 |
| ロ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ) ※加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間+700単位 | 781単位 |
別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次に掲げる指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につきそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

注8 乳幼児加算
| 78単位/日 |
指定福祉型障害児入所施設において乳幼児である障害児に対して、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき78単位を所定単位数に加算する。

注9 心理担当職員配置加算
別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。
イ 知的障害児の場合
| (1)定員10人以下 | 102単位 |
| (2)定員11~20人 | 51単位 |
| (3)定員21~30人 | 34単位 |
| (4)定員31~40人 | 26単位 |
| (5)定員41~50人 | 20単位 |
| (6)定員51~60人 | 17単位 |
| (7)定員61~70人 | 15単位 |
| (8)定員71~80人 | 13単位 |
| (9)定員81~90人 | 11単位 |
| (10)定員91~100人 | 10単位 |
| (11)定員101人~ | 9単位 |
ロ 自閉症児の場合
| (1)定員40人以下 | 26単位 |
| (2)定員41~50人 | 20単位 |
| (3)定員51~60人 | 17単位 |
| (4)定員61~70人 | 15単位 |
| (5)定員71人~ | 13単位 |
ハ 盲児又はろうあ児の場合
| (1)定員5~10人 | 102単位 |
| (2)定員11~20人 | 51単位 |
| (3)定員21~30人 | 34単位 |
| (4)定員31~40人 | 26単位 |
| (5)定員41~50人 | 20単位 |
| (6)定員51~60人 | 17単位 |
| (7)定員61~70人 | 15単位 |
| (8)定員71~80人 | 13単位 |
| (9)定員81~90人 | 11単位 |
| (10)定員91人~ | 10単位 |
ニ 肢体不自由児の場合
| (1)定員50人以下 | 20単位 |
| (2)定員51~60人 | 17単位 |
| (3)定員61~70人 | 15単位 |
| (4)定員71人~ | 13単位 |

注10 心理担当職員配置加算(公認心理師の場合)
公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(注9の心理担当職員配置加算を算定している福祉型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

注11 看護職員配置加算(Ⅰ)
指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅰ)として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 知的障害児の場合
| (1)定員10人以下 | 141単位 |
| (2)定員11~20人 | 70単位 |
| (3)定員21~30人 | 47単位 |
| (4)定員31~40人 | 38単位 |
| (5)定員41~50人 | 28単位 |
| (6)定員51~60人 | 25単位 |
| (7)定員61~70人 | 23単位 |
| (8)定員71~80人 | 20単位 |
| (9)定員81~90人 | 17単位 |
| (10)定員91~100人 | 14単位 |
| (11)定員101人~ | 13単位 |
ロ 盲児又はろうあ児の場合
| (1)定員5~10人 | 141単位 |
| (2)定員11~20人 | 70単位 |
| (3)定員21~30人 | 47単位 |
| (4)定員31~40人 | 38単位 |
| (5)定員41~50人 | 28単位 |
| (6)定員51~60人 | 25単位 |
| (7)定員61~70人 | 23単位 |
| (8)定員71~80人 | 20単位 |
| (9)定員81~90人 | 17単位 |
| (10)定員91人~ | 14単位 |

注12 看護職員配置加算(Ⅱ)
別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、看護職員配置加算(Ⅱ)として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 知的障害児の場合
| (1)定員10人以下 | 145単位 |
| (2)定員11~20人 | 96単位 |
| (3)定員21~30人 | 58単位 |
| (4)定員31~40人 | 41単位 |
| (5)定員41~50人 | 32単位 |
| (6)定員51~60人 | 26単位 |
| (7)定員61~70人 | 22単位 |
| (8)定員71~80人 | 19単位 |
| (9)定員81~90人 | 17単位 |
| (10)定員91~100人 | 15単位 |
| (11)定員101人~ | 14単位 |
ロ 自閉症児の場合
| (1)定員40人以下 | 36単位 |
| (2)定員41~50人 | 32単位 |
| (3)定員51~60人 | 26単位 |
| (4)定員61~70人 | 22単位 |
| (5)定員71人~ | 19単位 |
ハ 盲児又はろうあ児の場合
| (1)定員5~10人 | 145単位 |
| (2)定員11~20人 | 96単位 |
| (3)定員21~30人 | 58単位 |
| (4)定員31~40人 | 41単位 |
| (5)定員41~50人 | 32単位 |
| (6)定員51~60人 | 26単位 |
| (7)定員61~70人 | 22単位 |
| (8)定員71~80人 | 19単位 |
| (9)定員81~90人 | 17単位 |
| (10)定員91人~ | 15単位 |
ニ 肢体不自由児の場合
| (1)定員50人以下 | 29単位 |
| (2)定員51~60人 | 26単位 |
| (3)定員61~70人 | 22単位 |
| (4)定員71人~ | 19単位 |

注13 児童指導員等加配加算
常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。5の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(イにおいて「理学療法士等」という。)又は児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(ロにおいて「児童指導員等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、児童指導員等加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 理学療法士等を配置する場合
(1)知的障害児の場合
| (一)定員10人以下 | 151単位 |
| (二)定員11~20人 | 101単位 |
| (三)定員21~30人 | 61単位 |
| (四)定員31~40人 | 43単位 |
| (五)定員41~50人 | 34単位 |
| (六)定員51~60人 | 28単位 |
| (七)定員61~70人 | 23単位 |
| (八)定員71~80人 | 20単位 |
| (九)定員81~90人 | 18単位 |
| (十)定員91~100人 | 16単位 |
| (十一)定員101人~ | 14単位 |
(2)自閉症児の場合
| (一)定員40人以下 | 38単位 |
| (二)定員41~50人 | 34単位 |
| (三)定員51~60人 | 28単位 |
| (四)定員61~70人 | 23単位 |
| (五)定員71人~ | 20単位 |
(3)盲児又はろうあ児の場合
| (一)定員5~10人 | 151単位 |
| (二)定員11~20人 | 101単位 |
| (三)定員21~30人 | 61単位 |
| (四)定員31~40人 | 43単位 |
| (五)定員41~50人 | 34単位 |
| (六)定員51~60人 | 28単位 |
| (七)定員61~70人 | 23単位 |
| (八)定員71~80人 | 20単位 |
| (九)定員81~90人 | 18単位 |
| (十)定員91人~ | 16単位 |
(4)肢体不自由児の場合
| (一)定員50人以下 | 30単位 |
| (二)定員51~60人 | 28単位 |
| (三)定員61~70人 | 23単位 |
| (四)定員71人~ | 20単位 |
ロ 児童指導員等を配置する場合
(1)知的障害児の場合
| (一)定員10人以下 | 112単位 |
| (二)定員11~20人 | 75単位 |
| (三)定員21~30人 | 45単位 |
| (四)定員31~40人 | 32単位 |
| (五)定員41~50人 | 25単位 |
| (六)定員51~60人 | 20単位 |
| (七)定員61~70人 | 17単位 |
| (八)定員71~80人 | 15単位 |
| (九)定員81~90人 | 13単位 |
| (十)定員91~100人 | 12単位 |
| (十一)定員101人~ | 10単位 |
(2)自閉症児の場合
| (一)定員40人以下 | 28単位 |
| (二)定員41~50人 | 25単位 |
| (三)定員51~60人 | 20単位 |
| (四)定員61~70人 | 17単位 |
| (五)定員71人~ | 15単位 |
(3)盲児又はろうあ児の場合
| (一)定員5~10人 | 112単位 |
| (二)定員11~20人 | 75単位 |
| (三)定員21~30人 | 45単位 |
| (四)定員31~40人 | 32単位 |
| (五)定員41~50人 | 25単位 |
| (六)定員51~60人 | 20単位 |
| (七)定員61~70人 | 17単位 |
| (八)定員71~80人 | 15単位 |
| (九)定員81~90人 | 13単位 |
| (十)定員91人~ | 12単位 |
(4)肢体不自由児の場合
| (一)定員50人以下 | 22単位 |
| (二)定員51~60人 | 20単位 |
| (三)定員61~70人 | 17単位 |
| (四)定員71人~ | 15単位 |

注14 ソーシャルワーカー配置加算
障害児が指定福祉型障害児入所施設に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、社会福祉士又は5年以上障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援若しくは障害児相談支援に係る業務に従事した者(以下「社会福祉士等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 知的障害児の場合
| (1)定員10人以下 | 159単位 |
| (2)定員11~20人 | 79単位 |
| (3)定員21~30人 | 53単位 |
| (4)定員31~40人 | 40単位 |
| (5)定員41~50人 | 32単位 |
| (6)定員51~60人 | 26単位 |
| (7)定員61~70人 | 23単位 |
| (8)定員71~80人 | 20単位 |
| (9)定員81~90人 | 18単位 |
| (10)定員91~100人 | 16単位 |
| (11)定員101人~ | 14単位 |
ロ 自閉症児の場合
| (1)定員30人以下 | 53単位 |
| (2)定員31~40人 | 40単位 |
| (3)定員41~50人 | 32単位 |
| (4)定員51~60人 | 26単位 |
| (5)定員61~70人 | 23単位 |
| (6)定員71人~ | 20単位 |
ハ 盲児又はろうあ児の場合
| (1)定員5~10人 | 159単位 |
| (2)定員11~15人 | 106単位 |
| (3)定員16~20人 | 79単位 |
| (4)定員21~25人 | 63単位 |
| (5)定員26~30人 | 53単位 |
| (6)定員31~35人 | 45単位 |
| (7)定員36~40人 | 40単位 |
| (8)定員41~50人 | 32単位 |
| (9)定員51~60人 | 26単位 |
| (10)定員61~70人 | 23単位 |
| (11)定員71~80人 | 20単位 |
| (12)定員81~90人 | 18単位 |
| (13)定員91人~ | 16単位 |
ニ 肢体不自由児の場合
| (1)定員50人以下 | 32単位 |
| (2)定員51~60人 | 26単位 |
| (3)定員61~70人 | 23単位 |
| (4)定員71人~ | 20単位 |

2 入院・外泊時加算(1日につき)
| 定員 | 単位 | |
|---|---|---|
| イ 加算(Ⅰ) | 60人以下 | 320単位/日 |
| 61~90人 | 288単位/日 | |
| 91人~ | 252単位/日 | |
| ロ 加算(Ⅱ) | 60人以下 | 191単位/日 |
| 61~90人 | 172単位/日 | |
| 91人~ | 150単位/日 |
注1 イについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助の利用、介護給付費等単位数表第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用及び介護給付費等単位数表第15の1の2の2の注3に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。以下この2において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。
ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。
注2 ロについては、障害児が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は障害児に対して外泊を認めた場合であって、施設従業者(指定入所基準第4条の規定により指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者をいう。以下この第1おいて同じ。)(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該障害児に対し、支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として所定単位数に代えて、入所定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定福祉型障害児入所施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。
ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

3 自活訓練加算(1日につき)
| イ 加算(Ⅰ) ※障害児1人につき360日を限度 | 337単位/回 |
| ロ 加算(Ⅱ) ※障害児1人につき360日を限度 | 448単位/回 |
注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。
注2 イについてはロ以外の場合に、ロについては自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。
注3 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。

4 入院時特別支援加算
| イ 90日を超える入院期間が4日未満 ※月に1回を限度 | 561単位/回 |
| ロ 90日を超える入院期間が4日以上 ※月に1回を限度 | 1,122単位/回 |
イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに2の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位
ロ 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位
注 指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診療所(当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月につき1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

5 福祉専門職員配置等加算
| イ 加算(Ⅰ) | 10単位/日 |
| ロ 加算(Ⅱ) | 7単位/日 |
| ハ 加算(Ⅲ) | 4単位/日 |
注1 イについては、指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについては、児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
注3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 指定入所基準第4条の規定により置くべき児童指導員又は保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

5の2 家族支援加算
| 家族支援加算(Ⅰ) (月2回を限度) | 居宅を訪問(1時間以上) | 300単位/回 |
| 居宅を訪問(1時間未満) | 200単位/回 | |
| 事業所等で対面 | 100単位/回 | |
| オンライン | 80単位/回 | |
| 家族支援加算(Ⅱ) (月4回を限度) | 事業所等で対面 | 80単位/回 |
| オンライン | 60単位/回 |
- イ 家族支援加算(Ⅰ)
- (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- (一)所要時間1時間以上の場合:300単位
- (二)所要時間1時間未満の場合:200単位
- (2)指定児童発達支援事業所において対面により相談援助を行った場合:100単位
- (3)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合:80単位
- (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- ロ 家族支援加算(Ⅱ)
- (1)対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合:80単位
- テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及び家族等と合わせて相談援助を行った場合:60単位
注 指定福祉型障害児入所施設において、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、あらかじめ入所給付決定保護者(法第24条の3第6項の入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき2回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。
ただし、6を算定しているときは、算定しない。

6 地域移行加算
| (入所中2回、退所後1回を限度として)500単位/回 |
注 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、施設従業者が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

6の2 移行支援関係機関連携加算
| (月1回を限度として)250単位/回 |
注 指定福祉型障害児入所施設において、移行支援計画(指定入所基準第3条第1項に規定する移行支援計画をいう。以下同じ。)の作成または変更に当たって、関係者(都道府県、市町村及び教育機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は障害者総合支援法第77条の2に規定する基幹相談支援センターその他の障害児の自立した日常生活又は社会生活への移行に関係する者をいう。以下この注及び第2の4の2の注において同じ。)により構成される会議を開催し、当該移行支援計画に係る障害児への移行支援について、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め、必要な情報の共有及び当該障害児の移行に係る連携調整を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

6の3 体験利用支援加算
| イ 加算(Ⅰ) | (年2回、1回につき3日を限度として)700単位/日 |
| ロ 加算(Ⅱ) | (年2回、1回につき5日を限度として)500単位/日 |
注1 現に指定福祉型障害児入所施設に入所している障害児であって、重症心身障害児、重度障害児又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童であるもの(移行支援計画において体験利用が計画されているものに限る。)が、現に入所している指定福祉型障害児入所施設を退所する予定日から遡って1年間において体験利用を行う場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援を起こった場合に、1回につき3日以内(ロにあっては、5日以内)の期間について、2回を限度として所定単位数を加算する。
- (1)体験利用の利用の日における新たな環境への適応に対する支援その他の便宜の提供
- (2)体験利用に係る事業者その他の関係者との連絡調整その他の相談援助
注2 注1の体験利用は次に掲げる加算に応じ、それぞれ次に定める活動とする。
- (1)体験利用加算(Ⅰ)
障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の体験的な利用その他の体験活動(宿泊を伴うものに限る。) - (2)体験利用加算(Ⅱ)
障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動((1)に定めるものを除く。)

7 栄養士配置加算
イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
| (1)定員40人以下 | 27単位/日 |
| (2)定員41~50人以下 | 22単位/日 |
| (3)定員51~60人以下 | 18単位/日 |
| (4)定員61~70人以下 | 15単位/日 |
| (5)定員71~80人以下 | 13単位/日 |
| (6)定員81~90人以下 | 12単位/日 |
| (7)定員91~100人以下 | 11単位/日 |
| (8)定員101人~ | 10単位/日 |
ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
| (1)定員40人以下 | 15単位/日 |
| (2)定員41~50人以下 | 12単位/日 |
| (3)定員51~60人以下 | 10単位/日 |
| (4)定員61~70人以下 | 8単位/日 |
| (5)定員71~80人以下 | 7単位/日 |
| (6)定員81~90人以下 | 6単位/日 |
| (7)定員91~100人以下 | 6単位/日 |
| (8)定員101人~ | 5単位/日 |
注1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。
- (1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
- (2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

8 栄養マネジメント加算
| 12単位/日 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
- イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
- ロ 障害児の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種が共同して、障害児ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- ハ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、障害児の栄養状態を定期的に記録していること。
- ニ 障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

8の2 要支援児童加算
| イ 加算(Ⅰ) | (1月につき1回を限度)150単位/回 |
| ロ 加算(Ⅱ) | (1月につき4回を限度)150単位/回 |
注1 イについては、指定福祉型障害児入所施設が、現に入所している者であって、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であるものに対する指定入所支援について、児童相談所その他の公的機関又は当該児童の主治医等(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、当該障害児に係る会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議に参加し、児童相談所等関係機関との情報の共有及び連絡調整を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
注2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、要保護児童又は要支援児童に対して別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心理支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。

8の3 集中的支援加算
| イ 加算(Ⅰ) | (月4回を限度として)1,000単位/日 |
| ロ 加算(Ⅱ) | 500単位/日 |
注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定福祉型障害児入所施設に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行った時に、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
注2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた者であって指定福祉型障害児入所施設が、他の指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所施設をいう。第2の4の5において同じ。)を行う事業所、指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。第2の4の5において同じ。)、指定発達支援医療機関等から当該児童を受け入れ、集中的な支援を実施した場合に、3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

9 小規模グループケア加算
| イ 加算(Ⅰ) | 320単位/日 |
| ロ 加算(Ⅱ) | 233単位/日 |
| ハ 加算(Ⅱ)(9~10名の場合) 注 平成24年4月以前に建設された施設に限る | 186単位/日 |
| ニ 加算(サテライト型) | 378単位/日 |
注1 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。
ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第269号(外部リンク))の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。
注2 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物(当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能をゆうするもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合に、さらに当該障害児1人につき378単位を所定単位数に加算する。

9の2 障害者支援施設等感染対策向上加算
| イ 加算(Ⅰ) | 10単位/月 |
| ロ 加算(Ⅱ) | 5単位/月 |
- 注1 イについては、以下の(1)から(3)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、1月につき所定単位数を加算する。
- (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17条に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同上第8項に規定する指定感染症又は同上第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時などの対応を行う体制を確保していること。
- (2) 協力医療機関(指定入所基準第39条第1項に規定する協力医療機関をいう。以下同じ。)等との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この(2)において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
- (3) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区部番号A234-2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)若しくは医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診療の注11及び区分番号A001に掲げる再診療の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
- (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17条に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同上第8項に規定する指定感染症又は同上第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時などの対応を行う体制を確保していること。
- 注2 ロについては、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上、指定福祉型障害児入所施設内で感染症が発生した場合の対応に係る実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、1月につき所定単位数を加算する。

9の3 新興感染症等施設療養加算
| 月5回を限度として、240単位 |
注 障害児が別にこども家庭庁長官が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定共同生活援助等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

10 福祉・介護職員等処遇改善加算
| 項目 | 加算率 | |
| イ 加算(Ⅰ) | 21.1% | |
| ロ 加算(Ⅱ) | 20.7% | |
| ハ 加算(Ⅲ) | 16.8% | |
| 二 加算(Ⅳ) | 14.1% | |
| ホ 加算(Ⅴ) | (1) | 17.3% |
| (2) | 18.4% | |
| (3) | 16.9% | |
| (4) | 18.0% | |
| (5) | 14.6% | |
| (6) | 14.2% | |
| (7) | 15.2% | |
| (8) | 13.0% | |
| (9) | 14.8% | |
| (10) | 11.4% | |
| (11) | 10.3% | |
| (12) | 11.0% | |
| (13) | 10.9% | |
| (14) | 7.1% | |
- 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
- 注2 令和6年6月1日から算定可能
- 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

\事業者必須!/