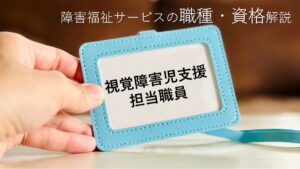障害福祉事業の「人工内耳装用児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次
「人工内耳装用児支援加算」の概要
「人工内耳装用児支援加算」とは、難聴児がより質の高い支援を受けられるよう、特定の福祉サービスに加算される報酬制度です。この加算は、特に人工内耳を装用している子どもを対象に、適切な言語訓練や支援を行う福祉事業者に提供されます。
対象となるサービスは、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」です。これらの事業所で、基準を満たした支援を提供することで、1日あたりの報酬に加算が適用されます。
この加算制度は、子どもの発達や社会適応を支援するために不可欠な存在であり、医療機関や教育機関と連携する仕組みも含まれています。その結果、人工内耳を装用する子どもたちがより良い生活を送れるよう支援の幅が広がります。
対象サービス
算定要件など
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)…児童発達支援
- 言語聴覚士の常勤配置
- 聴力検査室や他設備の設置
- 医療機関や学校との連携体制の構築
- 支援内容の記録および研修実施
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)…児童発達支援・放課後等デイサービス
- 言語聴覚士を1名以上配置(常勤換算不要)
- 支援相談や助言の記録作成
- 医療連携および適切な支援の提供
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
児童発達支援
| イ 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ) | |
| (1)利用定員20人以下 | 603単位/日 |
| (2)利用定員21~30人 | 531単位/日 |
| (3)利用定員31~40人 | 488単位/日 |
| (4)利用定員41人~ | 445単位/日 |
| ロ 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ) | 150単位/日 |
注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、
難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについては、言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
通所報酬告示第1の8の4の人工内耳装用児支援加算については、難聴児のうち人工内耳を装用する障害児(以下「人工内耳装用児」という。)に対して、医療機関等との連携の下で、言語聴覚士により指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 児童発達支援センターにおいて、指定児童発達支援給付費の算定に必要な員数に加え、言語聴覚士を1以上配置(常勤換算による配置)していること。
- イ 聴力検査室を設置していること。
ただし、支援に支障がない場合は、併設する他の設備に兼ねることができる。
- ウ 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。
- エ 人工内耳装用児への適切な支援を提供するため、人工内耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されていること。
- オ こどもが日々通う保育所や学校、地域の障害児通所支援事業所その他の関係機関(以下この⑫の4において単に「関係機関」という。)の関係者に対して、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
- カ 関係機関に対して、情報提供の機会や研修会の開催等,人口内耳装用児に関する理解及び支援を促進する取組を計画的に実施していること。
- キ オ又はカの取組を行った場合には、当該取組の実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 言語聴覚士を1以上配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)していること。
- イ 関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
相談援助を行った場合には、実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- ウ ❶のウ及びエを準用する。
放課後等デイサービス
注 言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している就学児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
通所報酬告示第3の6の4の人工内耳装用児支援加算については、2の(1)の⑫の4の(二)を準用する。
2の(1)の⑫の4
通所報酬告示第1の8の4の人工内耳装用児支援加算については、難聴児のうち人工内耳を装用する障害児(以下「人工内耳装用児」という。)に対して、医療機関等との連携の下で、言語聴覚士により指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 児童発達支援センターにおいて、指定児童発達支援給付費の算定に必要な員数に加え、言語聴覚士を1以上配置(常勤換算による配置)していること。
- イ 聴力検査室を設置していること。
ただし、支援に支障がない場合は、併設する他の設備に兼ねることができる。
- ウ 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。
- エ 人工内耳装用児への適切な支援を提供するため、人工内耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されていること。
- オ こどもが日々通う保育所や学校、地域の障害児通所支援事業所その他の関係機関(以下この⑫の4において単に「関係機関」という。)の関係者に対して、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
- カ 関係機関に対して、情報提供の機会や研修会の開催等,人口内耳装用児に関する理解及び支援を促進する取組を計画的に実施していること。
- キ オ又はカの取組を行った場合には、当該取組の実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 言語聴覚士を1以上配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)していること。
- イ 関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
相談援助を行った場合には、実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- ウ ❶のウ及びエを準用する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
参考:障発0330第16号(外部リンク)
Q&A
関連記事
まとめ
「人工内耳装用児支援加算」は、福祉サービスの質を向上させ、難聴児の発達を支える制度です。事業所はこの加算を活用することで、より高度な支援体制を構築でき、子どもたちの可能性を広げることが可能になります。
基準を満たすためには、言語聴覚士の配置や設備整備、医療機関との連携が求められますが、それらを整えることで、障害福祉のさらなる充実が期待されます。この制度を正しく理解し、活用することで、多くの子どもとその家族が安心して生活を送る手助けとなるでしょう。
あわせて読みたい
サービス横断メニュー