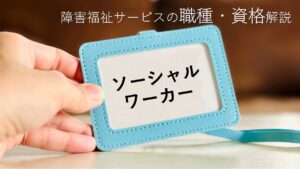「児童指導員等加配加算」の概要
「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。
この加算を受けるためには、資格を有する専門職を事業所に配置することが必要です。加配される職員には、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが含まれ、一定の経験年数と勤務形態が求められます。さらに、職種の異なる職員を常勤換算で配置することも可能で、サービス提供の質を向上させるために重要な役割を果たしています。
対象サービス
算定要件など
加配加算を算定するための要件
- 常時見守りが必要な障害児に支援強化を行う。
- 児童指導員等の専門職員を配置する。
- 経験年数や配置形態(常勤専従、常勤換算)を満たすこと。
加配職員の具体例
配置条件
- 配置された職員が常勤専従または常勤換算により、支援を強化する。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、児童指導員、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、
保育士又は当該事業実施区域に係る同上第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この第1において同じ。)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者、特別支援学校免許取得者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する特別支援学校の教員の免許状を有する者をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、児童指導員等加配加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
| 利用定員 | 単位 |
| (1)30人以下 | 62単位 |
| (2)31~40人 | 53単位 |
| (3)41~50人 | 42単位 |
| (4)51~60人 | 34単位 |
| (5)61~70人 | 29単位 |
| (6)71~80人 | 25単位 |
| (7)81人~ | 22単位 |
(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)30人以下 | 51単位 |
| (2)31~40人 | 43単位 |
| (3)41~50人 | 34単位 |
| (4)51~60人 | 27単位 |
| (5)61~70人 | 23単位 |
| (6)71~80人 | 20単位 |
| (7)81人~ | 18単位 |
(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)30人以下 | 41単位 |
| (2)31~40人 | 35単位 |
| (3)41~50人 | 27単位 |
| (4)51~60人 | 22単位 |
| (5)61~70人 | 19単位 |
| (6)71~80人 | 16単位 |
| (7)81人~ | 15単位 |
(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)30人以下 | 36単位 |
| (2)31~40人 | 31単位 |
| (3)41~50人 | 24単位 |
| (4)51~60人 | 19単位 |
| (5)61~70人 | 17単位 |
| (6)71~80人 | 14単位 |
| (7)81人~ | 13単位 |
(5)その他の従業者を配置する場合
| 利用定員 | 単位 |
| (1)30人以下 | 30単位 |
| (2)31~40人 | 26単位 |
| (3)41~50人 | 20単位 |
| (4)51~60人 | 16単位 |
| (5)61~70人 | 14単位 |
| (6)71~80人 | 12単位 |
| (7)81人~ | 11単位 |
ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ハに該当する場合を除く。)
(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
| 利用定員 | 単位 |
| (1)10人以下 | 187単位 |
| (2)11~20人 | 125単位 |
| (3)21人~ | 75単位 |
(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)10人以下 | 152単位 |
| (2)11~20人 | 101単位 |
| (3)21人~ | 59単位 |
(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)10人以下 | 123単位 |
| (2)11~20人 | 82単位 |
| (3)21人~ | 49単位 |
(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)10人以下 | 107単位 |
| (2)11~20人 | 71単位 |
| (3)21人~ | 43単位 |
(5)その他の従業者を配置する場合
| 利用定員 | 単位 |
| (1)10人以下 | 90単位 |
| (2)11~20人 | 60単位 |
| (3)21人~ | 36単位 |
ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合
| 利用定員 | 単位 |
| (1)5人 | 374単位 |
| (2)6人 | 312単位 |
| (3)7人 | 267単位 |
| (4)8人 | 234単位 |
| (5)9人 | 208単位 |
| (6)10人 | 187単位 |
| (7)11人~ | 125単位 |
(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)5人 | 305単位 |
| (2)6人 | 253単位 |
| (3)7人 | 216単位 |
| (4)8人 | 188単位 |
| (5)9人 | 167単位 |
| (6)10人 | 149単位 |
| (7)11人~ | 98単位 |
(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)5人 | 247単位 |
| (2)6人 | 178単位 |
| (3)7人 | 153単位 |
| (4)8人 | 134単位 |
| (5)9人 | 119単位 |
| (6)10人 | 107単位 |
| (7)11人~ | 71単位 |
(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)
| 利用定員 | 単位 |
| (1)5人 | 214単位 |
| (2)6人 | 178単位 |
| (3)7人 | 153単位 |
| (4)8人 | 134単位 |
| (5)9人 | 119単位 |
| (6)10人 | 107単位 |
| (7)11人~ | 71単位 |
(5)その他の従業者を配置する場合
| 利用定員 | 単位 |
| (1)5人 | 180単位 |
| (2)6人 | 150単位 |
| (3)7人 | 129単位 |
| (4)8人 | 113単位 |
| (5)9人 | 100単位 |
| (6)10人 | 90単位 |
| (7)11人~ | 60単位 |
留意事項
通所報酬告示第1の1の注8の児童指導員等加配加算は、指定児童発達支援事業所において、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(専門的支援体制加算を算定している場合においては、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置し、指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 児童指導員等を加配している場合については、通所報酬告示第1の1の注8のイの(1)から(4)まで、ロの(1)から(4)まで又はハの(1)から(4)までにより、当該児童指導員等の児童福祉事業に従事した経験年数(5年以上、5年未満)、配置形態(常勤専従、それ以外)、利用定員の区分に応じ算定すること。
児童指導員等とは、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(公認心理師、その他大学(短期大学を除く)若しくは大学院において、心理学科等を修了して卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者に限る)、視覚障害児支援担当職員(国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科の教科を履修した者若しくはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者をいう。
児童福祉事業に従事した経験年数については、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験も含まれる。
また、経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らないものであること。
配置形態について、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え1名以上を、・ 通所報酬告示第1の1の注8のイの(1)及び(2)、ロの(1)及び(2)並びにハの(1)及び(2)においては常勤専従により・ 通所報酬告示第1の1の注8のイの(3)及び(4)、ロの(3)及び(4)並びにハの(3)及び(4)においては常勤換算により配置していること。 - その他の従業者を加配している場合については、通所報酬告示第1の1の注8のイの(5)、ロの(5)、ハの(5)までにより、利用定員の区分に応じ算定すること。
配置形態については、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え1名以上を常勤換算により配置していること。 - 多機能型事業所の場合における常勤の取扱い
多機能型事業所によって行われる指定児童発達支援と指定放課後等デイサービスの場合において、例えば、当該指定児童発達支援の保育士と当該指定放課後等デイサービスの保育士とを兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 - 異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱い
通所報酬告示第1の1の注8のイの(3)から(5)まで、ロの(3)から(5)まで並びにハの(3)から(5)までを算定するに当たっては、児童指導員等又はその他の従業者を1名以上配置(常勤換算による配置)する必要がある。
このとき、児童指導員等とその他の従業者といった異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能とする。
児童指導員等とその他の従業者、また、経験年数5年以上の者と5年未満の者のように、算定する報酬区分が異なる場合は、以下のとおりとする。
- 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。
- 経験年数5年以上の児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。
- 経験年数5年以上の児童指導員等と経験年数5年未満の児童指導員等により常勤換算で1名以上とする場合 経験年数5年未満の児童指導員等の報酬を算定。
- 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。
- 本加算は常時見守りが必要な障害児への支援等の強化を目的としていることから、算定の対象となる児童指導員等及びその他の従業者については、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とすること。
Q&A
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
関連記事
-
「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
「心理担当職員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
報酬の留意事項 第三-(1):福祉型障害児入所施設
-
福祉型障害児入所施設:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
「視覚障害児支援担当職員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
放課後等デイサービス:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
「公認心理師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
報酬の留意事項 第ニ-2-(3):放課後等デイサービス
-
「児童指導員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
「保育士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
「理学療法士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
報酬の留意事項 第二-2-(6):難聴児経過的児童発達支援
-
「言語聴覚士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
「特別支援学校免許取得者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
報酬の留意事項 第二-2-(1):児童発達支援
-
児童発達支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
「手話通訳士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
「手話通訳者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
「作業療法士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
報酬の留意事項 第二-2-(7):重症心身障害児経過的児童発達支援
\事業者必須!/
まとめ
「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するための加算制度であり、障害児の福祉向上に貢献しています。
この加算を受けるためには、児童発達支援事業所に特定の資格を持った専門職員を配置し、所定の経験年数と勤務形態を満たす必要があります。
加配される職員には、児童指導員や理学療法士など多様な専門職が含まれ、加算が算定されるための要件を理解し、適切な支援体制を整えることが求められます。